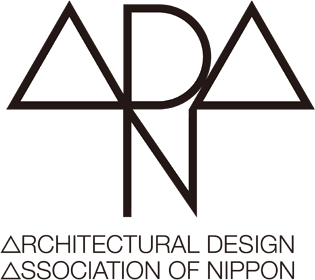修士設計コンセプトマッチ2015 公開ディスカッション
2015.11.14

2015年11月14日、京都造形芸術大学にて、神戸大学、京都工芸繊維大学、京都大学、東京理科大学、慶應義塾大学SFCの5大学7研究室の学生と教育が集い、コンセプト段階の修士設計プロジェクトの発表や、各大学での取り組みの紹介、そしてそれらを踏まえたディスカッションが行われた。
参加:宇野求、竹山聖、遠藤秀平、長坂大、松川昌平、角田曉治、ほか各大学の学生
司会・進行:西尾圭悟
それぞれの修士設計
宇野:発表してくれた皆さんお疲れ様でした。大学にそれぞれの傾向があって、修士設計に向けたプロセスはどこも違う。そこで、まずはそれぞれ発表してもらって、意見交換をすることが、今日プログラムです。無理に良いプレゼンテーションにするとか、テーマを揃えるんじゃなくて、そのまま聞いてみたいなと思っていました。それが聞けたんじゃないかと思います。大学や人によって全部違っていたので、そこが良かった。
では問題は何かと言うと、修士の設計というものを揃えていく必要があるのかどうか。それから海外の大学と比べたとき、欧米の大学では、エンジニアリングを加味したデザインワークをやっていたりします。そこで日本の修士設計をどう位置づけるか。どこまで、どういうふうに修士でやったらいいのか。それは学生も、大学で教える我々も、迷いがあるのではないか。
宇野:プレゼンテーションで、東京理科大学(以下:理科大)のここ数年の試みを紹介しました。自分たちとしては、サイエンスに裏打ちされたデザインを試みています。それが必ずしもうまくいっているわけではないんですが、面白いことをやってくれる人もいます。中には言うこと聞かない人たちもいて、修士設計がそれでいいのかと疑問に思ったりもします。どの程度コミットすればいいのかなとも考えます。
遠藤:神戸大学(以下:神大)では2011年から修士設計をはじめました。大学の方といろいろやりとりして、3年くらいかかってようやく修士設計で工学の修士号を出せることになりました。そこから試行錯誤しながら、修士設計とは何なんだろうと考えていたんですけど、学内だけでやっていても仕方がないので、先行して修士設計をやっていた京都工芸繊維大学(以下:工繊大)と一緒に「修士設計コンセプトマッチ」という名前で、修士設計について一緒に考えてみるイベントをはじめました。去年と一昨年で2回やりました。しかし、それでもなかなか答えらしきものは見つかっていない。どうしようかと考えていたところ、日本建築設計学会が立ち上がった。そこで、半分強引でしたけれど、宇野さんにこのイベントの委員長をお願いしたんです。
宇野:修士の設計は「発見する」とか、わからないから設計してみる、そこからできたものは何だろうと振り返ることが必要だと思います。学部とは違って新しい何かを試みること。それがうまくいくかどうかを含めて考えていくことですね。現代の先端的な問題を対象として、工学的な課題にしろ、社会的な課題にしろ、世界の道徳的なものでもいいけれど、しっかりとしたテーマを持って、建築的に答えを導き出すことが大切で、それが「建築とは何か」というのに近づいてくると思っているんです。
初めからある正解があって、それに向かって決まったトレーニングをして、たとえば課題で設計模型を同じようにつくらす。そういうのはよくないなと思うんですよね。竹山研究室の試みはどう転ぶかはわからないけど、すごくいいなと思いました。
自由になるステップ
竹山:今日のイベントのテーマは2つあると思っています。一つは、制度化された、いわば修士号をとるための修士設計がどうあるか。もう一つは、修士課程における設計教育がどうあるか。
僕が学生のころ、東京大学では修士設計のカリキュラムがまだまとまっていなくて、学生が勝手に「修士設計」と呼んでいたんです。学部のときは卒業設計という制度があって、課題があるのに対して、修士のあいだは東大でもとくに設計教育がなかった。最後に修士論文を書けばいい。ただし「修士設計」と呼ばれる科目があって、そのときは何やってもいい。原広司さんが「学部の卒業設計と同じものやるのはよくないな」という話をされて、たとえば同級生の隈研吾さんは、ル・コルビュジエのサヴォワ邸とガルダイアを、縮尺をデタラメにモノクロコピーして、ズバッと半分にしたり、それを切り合わせたりしたもの。それ1枚を提出した。卒業設計みたいに何枚も図面を描いたりするんじゃなくて、一つの作品としての「修士設計」というのが初期の東大ではあって、それは自分をすごく自由にしてくれたと感じました。そういうことがあってもいいと思っています。
宇野:当時の東京の建築系の大学院にとって隈さんや竹山さんの表現力は、衝撃的な事件だったんです。それまではモダニズムや機能主義が基本にあって、それをベースでやっていたんだけど、ガラッと学生たちの意識を変えた瞬間だったんだよね。少しずつそういう考え方が浸透してきた。学生が面白いことを自由にやってもいいんだって。
研究なしの建築学はありえない
宇野:一方で原広司さんがY-GSA(横浜国立大学大学院の建築都市デザインコース)ができたときのオープニングのスピーチで、「研究をしないで新しい建築学をつくれるのか」と言ったんですね。要するに「この大学院ではデザインしかしません」と言って外国のようなデザインコースを本格的に始めようとしていたんだけど、新しいものに挑戦しようとするときに、技を磨くだけではなくて、やっぱり常にどこかに研究という考え方が大切なんではないかと。そういう意味で言ったんですよね。
西尾(司会):今日の発表を通して各大学のテーマやその中のいろんな違いを共有でして相対化できたと思うんです。それぞれの取り組みを視野の広さや社会に対する問題意識、あるいは今まで建築について考えてきたことが、修士くらいになると言語化されて、収束されてくる段階にいますよね。他の人のそういうものを見て、率直にどう感じられたのか。学生の皆さんから言葉をいただきたいと思います。
遠藤:ひとり一言はしゃべってもらいたいですね(笑)。
リサーチからデザインへ
嶌岡(京大):修士2年の嶌岡です。工繊大ではまず研究をしてからそれを設計に生かすという形式をとっているのが、自分的には新鮮に感じました。工繊大の鳳山さんのように、たとえばアルヴァロ・シザが使っている角度を発見して、それを建築に生かす。そういうリサーチからデザインという流れがあったんですけど、京大では修士論文でリサーチだけではなくそれをまた理論化するわけですが、デザインというところまではいかない。そこをどのように取り組んでいるのかが気になりました。
鳳山(工繊大):私が「視野」というテーマについて考えるようになったのは、シザの研究をしたことをきっかけでした。ただ私のやり方はやっぱり主観的で、理科大や慶応の皆さんの発表を見た中で、たとえばコンピュータでシュミレーションして設計に生かしていくというような、論文からもう一段階の研究を今後していきたいと思っています。
大学を超えて修士設計の位置づける
司会:今日の発表の中で、慶応の学生さんと他の発表者と取り組んでいるときの感覚が違うんじゃないかと感じました。他の大学で、たとえば具体的に敷地を選んで設計をしてみる、ということとの違いについてどうでしょうか。
松川:うちが特別ではないと思うんです。一つはスタジオ制か研究室制か、大きく2つに分けられるんですね。また論文か設計か、というのが次の枠としてあったりする。あるいは今おっしゃった、特殊解でアウトプットするのか、より一般解でアウトプットするのか。そういういろんな二項対立の順列組み合わせで、どこもそのどれかにあてはまっていると思うんです。その中で今日集まった大学は、現状としてこういう修士の課程をもっていると。でもそこで、何らかの意思でそのやり方を選択しているというのも重要なんじゃないかと思っています。
司会:いま「意志」という言葉がありましたが、学生の皆さんは自分の大学の制度や環境の中で取り組んでいると思うんですが、それを超えて、自分が生きてきた中で取り組んできたテーマを、いま修士の段階になって反映させていくことに対して意志をもってやっているのか、というのが気になります。でもそのときに、ある種の自由さが許容される環境があるかどうかが重要ですよね。
長坂:大きなテーマで言えば、どこも割と自由なんじゃないかなと思います。でも話を聞いていて、確かにこれは違うなと思うものは、工繊大では「実践的に人間を育てる」というのがあるんですが、ヨーロッパのある大学で、修士は学生の段階でディテールまでしっかりやらせて、施主を説得するための準備までさせられる。つまり、修士の課程というのは、そこまで実践的に人間を育てるところなんだと。
うちの大学ではそこまではするつもりはないし、できようもないと思うんですが、ある種の実践力という点では、一定の能力をもった人を修士であると認めている気がします。結局は「修士」というものをどうジャッジしているのか。評価の仕組みがあって、設計の最終ジャッジは全体の講評会で一人ひとり判断するんだけれども、そのときに、たとえば竹山研究室でやってるようなことがテーマでも、それは「どっちの選択か」ということなんじゃないか。つまり非常に実践的なことを語っていようが、設計手法について語っていたり、既にある概念や考え方に対しておかしいと主張していても構わない。それが一定の概念化された域まで達しているかどうか。それは教員側から論理的にコメントできるようにしていきたいと思っています。
竹山:幸せについて語るかもしれないし、平和について語るかもしれない。それぞれ文化や風土が違っていいんだと。でもそれをどう評価するかというときに、やっぱり学生というのは、異文化に触れたり、むしろ論理を超えたところにもっていってもいいんじゃないかと思っているんです。そういう意味で、今日のイベントはとても面白いと思ったんですが、学生の皆さんがどう思ったのか聞きたいですね。

社会とつながる理論になっているか?
佐久間(理科大):修士設計は単純に思いついたことだけをポンと飛躍でやるのではなく、きちっとリサーチして、リアリティをもって説明できる、つまり理論をもった上で自分なりのテーマを探っていくというところが卒業設計とは違うのではないかと、全体的に見て思いました。
湯田(京大):竹山研究室で研究生をしている湯田と申します。今日の発表の中で、データの分析をしてそれを今後のまちづくりや建築に生かしていこうという話があって、そういう視点もあるのかと勉強になりました。でもそれを実際に建築化するときの、その手段やプロセスがあまりよくわからなくて、そこにまだ飛躍があるのかなと思ったんです。たとえばこれから設計活動をやる中で、データを活用するときの具体的な方法について考えられている方はいるのかなと気になります。
長坂:いまの言葉の中で、理論について言うと、自分の分野における「理論」という話と、もうちょっと広い社会に届くところまでの間を埋めていく「理論」の話は別にしないといけない。理論はあると言っても、世界のある部分で通じているだけではダメで、社会と結ぶところで話をしなければならない。湯田さんの質問は、その結ぶところについての「理論」が難しいのではないか、ということですね。
木本(工繊大):確かにその意味での理論が、今日の発表の中ではあまり説明されていない。それをこれからどう結びつけていくかが課題だなと思います。
司会:どう結びつけるか、その部分が問題ですね。理論だけで最後までいこうと思っても、きっとほとんどの人が問題に直面する場面がくる。それがこの修士設計の中で、もうきている人とまだきていない人がいるんじゃないでしょうか。
木本:学生の設計の段階では、社会と結びつける理論を考えようとしても結局、学生の設計のための設計になってしまう。社会と結びつく理論を考えてしまうと、きりがないんじゃないかと思います。
建築という実験
竹山:何年か前にうちのゼミで取り上げたんですが、ロンドンのAAスクールで、ピーター・アイゼンマンやダニエル・リべスキンドなど、世界中から建築家を集めて行った「セオリー・アンド・エクスペリメント(Theory and Experiment)」というテーマのディスカッッションがあったんですね。それはつまり、「建築は実験的なものに含まれる」という話で。でもそのディスカッションは、最後には「理論なんて言っても結局すべて政治じゃないか。建築家の理論も全部政治だ」と紛糾したんです。
木本さんは素朴に言ってくれましたが、社会と結ぶ云々言っても、建築は物理学の理論みたいにはなかなかならないでしょう。修士の段階では、ある程度自分たちで確認できる何らかの理論を考えてみればいい。「セオリー」っていうのは英語圏ではもっと幅広い考え方で、考え方とか哲学という意味ですね。「君の建築にはセオリーがない」というのは、「考え方がない」って言われているんですよ。日本語で「理論」と言うと、すぐに数学とか物理学とか思うから話がややこしくなる。建築もそういった思想とか考え方があってもいいと思うんですけど、それを理論化して武装すると政治になる。もう少し学生ならではの実験的なやり方とか、それと結びつくような実験に近しいものの考え方みたいなものが、僕はいいんじゃないかと思います。
宇野:建築の設計にも原理や法則と呼べるようなものがあるのならいいんだけど、なかなかそこまでは言えない。でも、やっぱりなんらかのポリシーが設計者にないといけない。動物や植物や自然物とは違って、建築は人が人のためにつくる人工物です。だからポリシーとポリシーがぶつかることがあるわけです。それをまとめるときに、何かやっぱり理屈がいる。その理屈というのは物理の法則とは違って、ある種の合意を形成するためのもの、つまり、妥当かどうか。時代精神であったり、共感を呼ぶものであったり。
皆さんは若者だから敏感に何かを感じている。それに期待して今日僕らも一生懸命に皆さんの話を聞いているわけです。僕たちみたいに建築を何十年もやってる方が、ある意味で上手いのは当たり前で、そうじゃなかったら僕らは死んだ方がいい(笑)。でもあなたたちは経験で勝負するわけではない。自分で良いなと思ったことに、自信をもってやっていいんじゃないかな。
竹山:建築のジャンルでは、理論というものをもう少し噛み砕いて考え、説得力と言い換えたり、合意形成と呼んでいたりする。つまり、何らかの論法とかロジックがあればいい。今日のプレゼンテーションの内容でも、それが普遍的な真理であるかどうかではなく、信念があれば説得力をもつと思う。
あと補足すると、理論とか説得力とか話しているけど、松川さんの研究室の方向は「方法」をとってるから、これはすごく明快ですね。社会的な説得力とか、合意形成とは違う、何か形を生成する原理みたいなものを考えているように感じました。
長坂:物理学や数学の話の方のロジックでいくと、「合意形成=正しい答え」となるからおかしな話になってしまう。合意形成をするための話し合えるような場がきちんと設定されればいいけれど、たぶん多くの迷っている人は皆、自分の最終的な答えが良いんだと言わんがためにロジックをつくっていく。それだとつまらないと思う。その間の線引きは、自分自身の課題の中では、実はなかなか難しいんですよね。今日はその意味では、人との差異が少し見れたかなと思います。
遠藤:まだ途上の人が多いので、こういう場で議論することを通して、先に行って欲しいと思います。

修士設計を巡るいまの状況
宇野:東京では修士設計を何となくやっている大学は20以上ある。そういうのを持ち寄った展覧会が3つあって、一番歴史があるのがJIAの関東甲信越支部の「大学院修士設計展」で2003年からやっている。それはプロフェッサーアーキテクトの有志が一生懸命セッティングしています。もう一つは「トウキョウ建築コレクション」。これはヒルサイドテラスが会場ですが、全国から参加があって、卒業設計よりは密度のあるディスカッションしている。あとはレモン画翠さんがやっている非常に大規模な展覧会があって、その中でも修士設計展もある。簡単な審査と講評をしてるくらいでしょうか。それらは評価基準の問題にしても、ディスカッションの内容にしても、イベント的だという印象があります。そこをもうちょっと修士の設計では、建築の議論を通してやったほうがいいんじゃないかなと思っています。関西では神大と工繊大が修士設計をやっていると聞いて、それなら東京でやってることとは違うことをやれるんじゃないかと。そこでまずは人数は少ないけれど、それぞれのプロジェクトをもち寄って、建築の話をしてみたいと思ったんです。
それは日本の建築系の大学に一番欠けている部分で、海外の人と接したときにすぐわかるんです。つまりプロジェクトをやっても、留学しても、やっぱり論理がないんですよ。日本は若い人の設計はドローイングはいいし、感覚的には優れている。ガラパゴスだから面白い状況があって、その中で面白いもの、変な花とか、不思議な動物とか、すごく綺麗な鳥のようなものを、いっぱいつくっている(笑)。でもそれを説明する言葉をもってない。やっぱりこれからは説明する言葉を使えないといけないんじゃないかなと思うんです。そのときに、今日のような試みは大切なんじゃないか。
修士設計を巡るいまの状況
松川:卒業設計は学部の学生が初めて自分で課題をつくるという過程の経験じゃないですか。それまでは先生のつくった課題に応えるということしかしてない。卒業設計で初めて自分で敷地を選んで、問いそのものを自分で立てる。では修士設計が卒業設計と何が違うのかと考えたときに、自分で立てた問いに対して自ら答えを出すための方法論がついてるかどうか。それが分かれ目かなと僕の中では思っています。昔の菊竹清訓先生が言われた「か・かた・かたち」の三段階論みたいなことだと思うんですけど、まずビジョンがあって、方法論があって、形が決まってくる。この三段階が揃って初めて一人前になるとすると、学部生のころに形をつくることを学んで、卒業設計で問いを自分で立てるようになって、修士でそれの方法論までつくる。そうすると一巡するのかなと。うちの研究室では「かた」、つまり方法論を掲げてやっているという背景があります。
遠藤:学部の卒業設計は結果に対する評価だと思うんですね。最終的に素晴らしいプレゼンできました、と。途中何していようがそこは問わない。修士設計では、もちろん結果もあるけれど、そのプロセスを評価の対象にしたい。理論というある種のまとまりがある部分だけでなく、それをどうやって生み出すか。それをとらえないといけない。結果に対する同意とか合意ではなく、プロセスに対する合意がちゃんとものになってるかどうかじゃないかと思います。
制度が揺らぐ現代で
長坂:遠藤さんがされた話を非常に制度的でカタい言い方すると、学生にもときどき言ってるんですけど、「自分がただ好きなものを一生懸命語っただけでは出られないよ」と。大学の修士という一つの資格を与えるわけです。その資格制度を通すための問題まで自分でつくっているわけだから、方法論なら方法論において、ある水準に達していることを示さなければいけない。誰もが既に課題としてもっているようなある種の枠組みの中で示せる場合はいいけれど、そうじゃない枠組みの中では、たとえばその方法論がどういうふうに位置づけられているかも、自分で言わなければならない。そこが大変難しいところなんだと思います。
松川:長坂さんはそういうときに、屁理屈と理屈の違いをどうやって教えてらっしゃいますか?本人は理屈だと思ってるんだけど、他の人から聞くと屁理屈に聞こえるというところが問題だと思うんです。
長坂:教育的には、「いま君が言ってることはここまではわかるけれども、ここからはわからない」ということを言い返していくしかない。ここから先は理解できません、通じてません、というふうに。
宇野:いまの話は本質的で、つまり建築というのは制度だ、という話をしてるんですね。国が資格を決めて、教育をして、建築の大学に行ったら建築家なれる。それはどこの国でもやってることだと。だけどどこで線引きをするのか、どういう評価基準にするかが問題なんですよね。大学も制度だし、建築も制度で、二つの制度がかなり揺らいでるわけです、現代では。
長坂:工繊大では一級建築士をとることと、修士をとることが同じなので、つまり「ここはやっていなくてもOK」というのはないんですよ。全部ある程度やってないと出さない。日本の場合は一級建築士の国家試験があるので、うちの大学ではここまでOKをだしますよ、と言ってしまうこともできる。でも社会の中では、大学が出す修士号というのは一定の評価が得られてしまいますからね。
世界から見た日本、日本から見た世界
宇野:いまの若い人が気をつけなければいけないことは、日本の大学制度では建築系の学生をものすごくたくさんつくりだしている。ヨーロッパでは建築家の数は国民一人あたりで言うと10分の1とか20分の1とかだから、建築の大学を卒業すれば、ハードルが高いことも確かですけど、それで食べていけないことはない。それでもヨーロッパでは建設量が非常に少ないし、階層社会で窮屈さもあるから、景気がよくないと仕事がない人たちは発展しているアジアに来たがりますよ。日本は人気がある。楽しいし、食べ物も美味しいから。でも日本から見ると、ヨーロッパとか海外ってすごいよねとか言ってて、何かミスマッチングを起こしている。若い世代にとっては、自分たちが世界のどういうポジションにいるのか、また歴史的にはどこにいるのかを、もう少し見据えておかないとね。日本の建築や大学の制度の混乱した状況の中にいるから、注意した方がいいかもしれない。だからいま修士の建築設計って何なんだというのを、手探りでみんなで議論するっていうのは、若い人たちにとってとても意味があると思います。
歴史の文脈を見つめながら
宇野:最近邦訳が出たマリオ・カルポの『アルファベットそしてアルゴリズム』という本があって、その中で彼が言っているのは、ルネサンスにはアルベルティの建築論があって、一応体系的にまとまっていた。だけどそれは言語で語られた建築論だった。その少しあとに、木版の技術が出来て聖書がたくさん印刷されたように、図面を使って建築を体系化する書物が一気に出る。ルネサンスが非常にそれまでの建築を体系化して、かつ印刷して書物にできるから、パースによって建築を構成するという論理が生まれたりする。パラディオも建築論を書いているんですが、あれは建築カタログなんです。こういう固体や材料がありますよ、だからこういうプロポーションなんです、それでこのくらいスパンが飛びますよ、ということが全部書いてある。だから彼はお客さんのところに行って、イオニア式でいきますか?コリント式ですか?と、そういうふうにやっていたに違いない。そうして一応体系化されたので、世界がそのあともルネサンスを大切にしていく。工業時代になって機械が誕生すると、大量生産できるようになる。新古典主義がでてきて、たとえば列柱が並ぶような大規模な駅舎がつくられたりする。そして20世紀になったときに、装飾は破壊されて近代主義の建築が完成する。要するに、印刷と機械の技術が建築を大きく変えてきたというわけです。
ところが今はコンピュータがでてきた。問題は、コンピュータは完全に計算機だから、何回変更しても気にしない。そうやってパラメータを変えれば、いろんな形態をだすことができるようになった。この変化は大きくて、建築をデザインすることと実社会との関係が、僕らが大学に行っていたときとはまったく変わってしまいましたよね。
そこで社会とどう接するかを考えたときに、ちょうど修士の皆さんは中間的な立ち位置にいますよね。大学の中にいつつも、社会のことがすごく気になっているはず。そこをもう少し本音で話してほしいなと思います。
キム(京大):竹山研究室は修士論文だけをやっていますが、ゼミで修士論文のチェックと学部4回生のエスキスを平行して見ていると、先ほど先生もおっしゃっていたように、卒業設計では自分なりの理論があって、自分の思っていることを人に伝えて、それが理解されれば問題ないという感じなのですが、修士論文では客観的な論理に沿っていなければいけないということがあると感じています。
僕は、建築士になることが制度上の話であるのに対して、建築家というのは自分が名乗ればなれるものというふうに思っています。建築の理論もそれと似ていて、自分が理論です、と言えばそれでいいのではないかと思っています。乱暴な言い方かもしれないのですが。それぐらいの気持ちでやっていきたいという意味も含めて。
多様な視点からとらえ直すための場
司会:では最後に神大の加藤さんに全体の総括をお願いしたいと思います。
加藤(神大):いつもは大学内の講評ばかり見ているので、今日は他の大学の発表や講評を実際に見れるよい機会でした。神大の修士設計はだいたい概念的なものを調査して、分析して、そこから形とか道筋をつくっていって、建築に落としこんでいくというのがよくあるパターンなんです。でも自分でやってみると、理論とか手法だけを信じて設計していても何かパンチのあるものはできないし、かといって自分の主観だけでいきすぎると修士設計ではなくなってしまう。そういった修士設計とは何だろう?というスパイラルに陥っていました。
今日のイベントの前にそんな葛藤があったんですけど、今日の講評会で、この建築の意味は何だとか、良さは何だということを問われて、やっぱり理屈だけにとらわれていたらいいものはできないんだなとか、また設計する上では、その土地を見て、自分で考えて、手法は生かしながら設計していくのがいいのかなと思いました。理論に関しては、自分が修士設計をするためにつくった手法ではありますが、でも現地で実際に登り窯をみて、集落の人たちの会話を手助けするような、本人たちが気づいていないものを建築の空間にするようなものでもあることは確かだなと。そうしたいろんな見方が今日の会で発見できたので、これを生かして今後の設計を進めていきたいと思います。
遠藤:ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。
竹山:こういう会をどんどん大きくしていく上で、やっぱり引き継いでいくことが大事ですね。