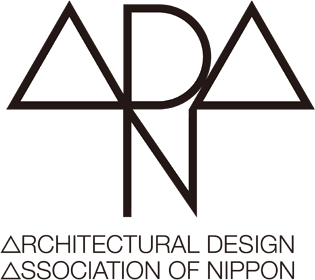アジア建築学生サマーワークショップ in 大阪&鯖江
2016.08.29
レポーター:西尾圭悟8月18日から29日にかけて、「アジア建築学生サマーワークショップin 大阪&鯖江」が開催された。今年はじめての開催となるこの企画は、アジアの11ヵ国から24人の学生が参加する滞在型の国際ワークショップである。
大阪と京都の建築を見学するツアーも足早に組み込まれているが、スケジュールの大半は福井県鯖江市の河和田という集落に滞在する。河和田は、「うるしの里」と呼ばれ、主に漆器を中心とする伝統工芸を産業としてきた。近年では、海外で「うるし」が注目されはじめ、海外からの訪問者も増えつつある。また京都精華大学の学生らが長期滞在し、アート作品やイベントの企画などを行う「河和田アートキャンプ」が今年で12年目を迎えている。地域外から訪れるものをもてなす心をもった地域性も魅力の一つだ。この企画も、鯖江市をはじめ、地元のボランティアの温かい支援により成り立っている。

今回参加してくれたのは、ネパール(トリブバン大学)、インドネシア(インドネシア大学)、台湾(實踐大學)、韓国(弘益科学技術大学)、中国(東南大学)、インド(PVP建築大学)、ミャンマー(ヤンゴン工科大学)、カンボジア(カンボジア王立芸術大学)、シンガポール(シンガポール国立大学)、タイ(タンマサート大学)、モンゴル(モンゴル科学技術大学)の11ヵ国からの学生19人に、日本から近畿大学、立命館大学の5人を加えた24人。海外からの参加者のほとんどは、日本に来るのは今回がはじめてだと言う。
ワークショップは8人1チームの計3チームに編成されて行う。同じ国からの参加者は別チームに分けられるため、チーム内では全員国籍が異なっている。今回の課題は、家具より大きく、建築より小さい「Pod Architecture」(まゆ・さやの意味)を、河和田のどこかに敷地を設定して制作すること。また竹をはじめとする地域の材料を活用することが条件として設定された。

19日に河和田に入り、26日には、完成した作品の最終講評がある。およそ7日半で設計から、制作、プレゼンテーションの準備までを完了させる。スタジオマスターは、全体のディレクターの務める堀口徹(近畿大学)に、建築家の森田一弥、梅原悟を加えた3人。デザインや技術的な指導を行うだけでなく、ほとんどの時間を学生たちとともに過ごし、全面的にサポートする。

期間中には、構造家の萬田隆(神戸芸術工科大学)や、家具スケールから建築までの設計・施工を行う山下麻子(GENETO)らが河和田まで駆けつけ、制作のアドバイスとレクチャを行った。また越前和紙の人間国宝である岩野市兵衛の工房を訪ね、日本のものづくりに触れる貴重な機会を得ることができた。学生たちは単に制作を進めるだけでなく、これらのプログラムを通して刺激を受けることができたようだ。

2日目の中間講評でコンセプトは固まりつつあったものの、構造や、部材の処理などのスタディが続き、材料の調達や加工などを経て、最終的な制作期間は2日半と当初の予定よりかなりの短期間であった。
参加した学生のほとんどが学部2~3年生だが、時には夜遅くまで議論を行うなど、真摯に取り組む姿勢が見受けられた。また、親しくコミュニケーションをとりながら、チームとして、またワークショップ全体としての一体感をつくり出していった。

最終講評には、竹山聖(日本建築設計学会会長・京都大学)、遠藤秀平(神戸大学)、倉方俊輔(大阪市立大学)の3名に加え、牧野百男(鯖江市長)も駆けつけ、実際に河和田のまちの中に設置された3作品を歩いてみて回った。

チームA 「ribbon」
通常は破棄される皮を残して製材した木材を立体的に波打たせながら、広場のベンチを包み込んで影をつくるように組み上げた。

チームB 「WATER POD」
河和田の高台に位置する神社の境内を敷地に、神聖な雰囲気と対峙しつつ、集落の風景を切り取るフレームをもった茶室のような小空間をつくった。

チームC 「mountinue」
階段状の構造と、竹を曲げてつくった手摺からなる。視点をシフトさせることで、河和田の自然を地元の人に日常とは異なる視点で見てもらいたいという思いが込められた。

現地審査と、公開プレゼンテーションを経て、「場所性」「構築性」「空間性」の3つの観点から、それぞれ「市長賞」、「設計学会賞」、「スポンサー賞」が与えられた。同じ課題、同じ条件で、限られた期間と材料を用いながら、3作品が建築として似通ることなく独自のコンセプトをもっていたことで、講評も充実したものになっていた。

いずれの作品にも、河和田の自然に対する強い敬意が込められていたことは、印象的だった。国籍は様々ながらもアジアの国々から集まった学生チームであることが、3つの作品の根底にあるのかもしれない。また河和田という田舎の環境が、少しずつ参加者全員の心身に浸透していったことは、想像に難くない。
また一方で、すべての作品が、特定の1人の作家性に陥ることなく、シンプルかつユニークな構成によって、場所を愛しながら、場所の価値を再編し、新たな価値を獲得するという、建築のちからを発揮した作品に仕上がっていた。参加学生のそれぞれの力が、離散することなくチームワークによって結集された成果であることを物語っている。
後日、3作品は地元の新聞に、「変わった建築」と評されることになるが、その「変わった」とは、凡庸なものではなく、それぞれが確かなオリジナリティを確立していたことの現れではないだろうか。