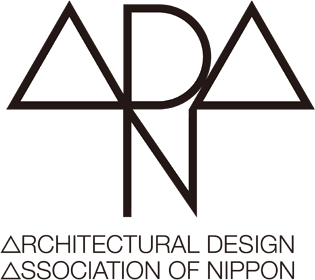伝統に逆らう建築 近世から伝統論争にいたる日本建築における生産様式の変容
ARCHITECTURE AGAINST TRADITION
Transformation of Modes of Production of Japanese Construction, From Premodernity to the Debates on Tradition
ガブリエル・コーガン、*1田村将理*2
Gabriel Kogan *1 & Masamichi Tamura *2
This article aims to critically understand how Japanese modern architects in the context of the so-called Debates on Modern Architecture in 1947-1948 and Debates on Tradition in 1953–1957 advocated overcoming premodern modes of production in favor of developing forms of construction based on the use of industrial techniques and associated productive forces. Through the reexamination of primary sources from the period, this essay reframes these debates on modernity and tradition to reveal their underrepresented socio-technological aspect and reformulate it into a critical perspective to recontextualize Japanese post-war architecture in the 1950s and beyond.
Key Words : Tradition, Construction, Modern Architectural Production, Dento Ronso, Kenzo Tange
本稿は、「近代建築論争」(1947-1948)および「伝統論争」(1953-1957)(註1の文脈において、日本の近代建築が工業技術、とりわけ鉄筋コンクリートを利用した建設のありかたを発展させるために、いかにして近代以前の生産様式の克服を提唱したかを把握することを目的とする。
まず、本稿は近代建築家たちの標的となった江戸時代(1603 - 1868)以降の前近代的な生産様式について検討する。(註2次に、1868年の明治維新における近代化から1940年代半ばにいたる欧米からの技術的知識と素材の導入を概括し、戦後の近代主義的な前衛の興隆以前からすでに水面下で進行していた転換を明らかにする。そして、1947年から1957年にいたる近代建築家の作品と論考の言説分析に基づき、戦後の新たな生産手段の普及を肯定する理論的・建築的な言語を近代建築課がいかに展開してきたかについて代替的な視点を提示する。これらの議論を通じて、本稿は近代建築家たちが前近代的な労働組織にいかに遭遇し、職人が発展させてきた建設技術を新たな工業生産の論理においていかに内面化し、政治的に中性化しようと試みてきたかを検討する。
この目論見に立ち、本稿は(1)川添登と丹下健三を筆頭とする近代の建築家及び批評家が20世紀半ば以降に建設現場における前近代的な建築生産の痕跡をいかに近代建築に取り込み、それによって中性化しようとしてきたかを把握し、(2)いわゆる伝統論争について、縄文と弥生の美学的対立のみに着目する主流の視点を疑い、1953年から1957年に展開した論争の主要因のひとつとしての技術的・建設的な諸問題を明らかにすることを目指す。
本稿の著者は、主たる参考文献として1953-1957年当時の新建築に掲載された50以上の記事を分析した。(註3 本稿の方針において、著者の調査したかぎりで前身にあたるのは、一次資料(伝統論争に参加した一部建築家の記事)の幅広い分析に基づいた布野修二(布野 1981)の研究のみである。本稿は生産様式の変容に着目することで、布野の研究を40年後の現在から新たな批判的視座を通じて分析することを試みる。
江戸時代(1603-1868)における近世の生産様式:
職人仕事と建設現場
日本においては、欧州でルネサンス以降「建築」と呼ばれたものにあたる概念や用語は19世紀半ばまで存在していなかった。この「建築」という表現は国民国家の創出の最中にあった明治期(1868-1912)に、英語のArchitectureの翻訳として登場した。この移行期において、建築家・建築史家の伊東忠太は1886年の創設以来「造家学会」と呼ばれてきた建築家の連盟を「建築学会」に改名することを1894年に提唱した。当時、家づくりを意味する「造家」と概ね建物の構造を示す新語としての「建築」の訳が併存していたが、伊東の提唱はarchitectureの訳語を「建築」として確立したものとみられる。伊東はこれらの用語を峻別するために、造家を「industrial arts」(工業技術)に、建築を「fine arts」(芸術)になぞらえ、後者を奨励した(Ito, 1894)。そして1897年には建築学会への改名が行われた。(註4
この言語的な変化は、生産様式の広範な転換を反映していた。後述するように、建築家や技士が初めに準備する集権的な図面一式が階層化された作業工程を貫通することで平面図が建築に投影されるルネサンス以降に普及した近代ヨーロッパの考え方とは異なり、19世紀半ばまでの日本の建設は、職人や、それ以前は工匠と呼ばれていた人々の手仕事のノウハウに大いに依拠していた。(註5
図面の不在から浮上するのが、明治維新(1868)の文脈で展開した近代化のための様々な変革以前の建設現場では、生産チェーンがどのように形成されていたのかという問いである。また、たとえば江戸時代のような近世の文脈においては、建設現場における労働組織の基本的枠組はどのようなものであり、意図や要求はどのように伝達され、建設をめぐる様々な意志決定はどのようになされていたのだろうか。こうした問いのすべては、前近代から近代への移行における建築的実践の転換や遺産や記憶を再び歴史的に文脈化することへとつながっていく。これを足掛かりとして、本稿は丹下健三のような近代建築家の「伝統」観の批判的考察を行う。以下、本稿は日本が前近代から近代へと向かうなかで建設に生じた本質的な変化と、その流れのなかでは変わらず、後に建築家たちが変えようとしたものについて検討していく。
江戸時代における政府主導の大規模事業(寺社や城郭や宮殿)は、将軍や大名や皇族などの建設資金供与者の要望から始まるものであり、建設には多数の職人が従事した。(註6 これらの複雑な建設事業は、管理能力を有した職人らが労働力の組織役として幕府・諸藩に雇用される機会を生み(太田 1947)、管理業務と現場業務の分業化を導いた。とりわけ1632年以降は、労働組織の階層構造に新たに役職が置かれ、管理業務や意思疎通や建設現場の仲介を委任された作事奉行やその部下にあたる作事方のような官僚的立場が登場した(太田 1947, 179; Coaldrake 1990&1996)。
権力者の建設現場への指示は、職人の任命、口頭や文書による決定、建物の場所や規模といった一般的側面に影響する建物の機能と様式との関係等について最初の判断を行うことができた。しかし、これらの指針は建設のディティールや技術的な方法にまでは踏み込むことはできなかった。大名も委任された作事奉行も、手仕事についての経験や知識の不足のため、建設現場における労働を徹底管理するための決定的な道具を有していなかった。権力者の要求が最終的に建設職人たちによって完全に満たされることはなく、この過程において数々の対立が生じた(Coaldrake 1996)。生産組織の責任者として、棟梁に任じられた職人は外部からの命令を嫌っていたといわれている。(註7
幕府上層の意思決定領域から下される一般方針は、作事奉行を通じて、棟梁と呼ばれる代行者(時代や立場により、大工頭という名称もある)へと伝達され、これらの棟梁が建設現場における労働組織の責任者となった(明治前日本科学史刊行会 1961)。さらにこれらの代行者は、階層的な労働組織の上層部とは異なり、職人としての広範な技能訓練に加えて、建設技術にも精通していた。ひとつの現場に二人以上の棟梁が置かれることもあり、大工棟梁や左官棟梁や鳶棟梁のようにそれぞれの職域の責任を負った。この他にも、屋根や鋳鉄や壁塗りや畳や石工や扉など、様々な分野に精通した職人がいた。熟達した職人の通称として親方という言葉も用いられていた。
大工棟梁は木造軸組工法を担う大工として柱の位置や柱間を管理し、建設行為の一般的な諸側面を画定するうえでより大きな責務を有していたが、現場の職人集団はそれぞれが担う要素と専門性に大きな自律性を有していた。今日の労務関係とは異なり、個々の要素や装飾や技術的解決がどのようなかたちになるかを階層上部が厳密に規定できる機構はなかった。棟梁たちは建設の各部分にそれぞれに専門化していたため、建設の全工程を垂直的に貫通することは誰にもできなかった。たとえ建設現場全般の責任を担う棟梁(大棟梁)がただ一人置かれていた場合でも、その棟梁は建物を構成する様々な側面のひとつを出自としており、他の分野についてのノウハウは備えていなかったのである。
仕事の場を中心として、仲間と呼ばれる非公式の職人組合に基づいていたこの労働組織において、棟梁や親方は知識を見習いに伝授し、職人集団を形成していた(稲垣 1959, 51-51, 59-60 ; Coaldrake, 1990)。こうした仕事の性質は建設現場における職人的・手工業的な生産の協働的ネットワークとして定義しうるものであり、そこではすべての棟梁同士と各々の率いる集団内部において、日常的な実践とノウハウを通じた対話の場が常に成立していた。各々の非公式の職人組合の内部には―ドローイングという権威の不在において―、フェルロ(2010, 2018, 2021)が「定常的で制度的な分業」と呼んだものは存在せず、そのことについては建物を構成する建設要素の独立性を特に考慮することもできる(稲垣 1959, 51-51, 59-60)。(註8
江戸時代における建物の新設に関わる階層的な構造は、著者による文献調査 (稲垣 1959; 明治前日本科学史刊行会1961; Coaldrake 1990 & 1996; Clancey 2005; 日建協 2001; 坂本・鎌田 2017; Ota 1947; Curtis 2011; Bon & Yoshiro 2018, 山岸 2017)に基づき、大まかには以下のような基本構造へと整理することができるだろう。ここにはすでに請負/管理と建設現場の層の予兆的な分化が生じている。
請負/管理の層:
建設資金の供出者 (例:大名、将軍)
事業統括者(例:作事奉行、御被官大工)
土木や建設技術の管理者(例:普奉請行)
建設現場の層:
建設現場の統括者 (例:大棟梁、大工頭)
構造・大工技術の統括者(例:大工棟梁)
建設労働者の統括者(例:親方)
熟練した建設労働者 (例:職人、大工)
非熟練の建設労働者 (例:見習、徒弟)
ここで重要な点は、建設の全工程を貫く完全な技術的熟練を有する単一の専門家がいないことと、これらの工程間の仲介役としてのドローイングが登場していないことであり、このことはこの建築研究で度々軽視されてきた側面といえる。技術的な図面による正確なトップダウンの作業指示の不在は、現場の労働者がスキルと集合知を活用し、与えられた業務を単に遂行するよりも積極的に建設に参加する機会を与えた。したがって、この建設現場のボトムアップの応答においては、構想と施工はむしろ一体的で、設計と生産の分離や建築・構造の専門事業体と建設現場の分離に基づく建築とは異なっていた。技術的図面という権威の不在は労働組織に異なる関係性を付与し、それは生産における上層と現場の調停にも、実践やノウハウを通じて絶え間ない対話関係を築くことを必要とする建設現場の日常における関係者間の関係にも現れる。
1868年の明治維新以前は、一般的にドローイングは建設の指針となるデザインの投影というよりも建設を終えた構造の事後的な記録に用いられていた。建物一式の全体図面は既存の建築の登録や、建物の再建や、職人の工房における教材として用いられた。コールドレイクは日本建築についての[英語圏における]権威的な著書『Architecture Authority in Japan』で、江戸城の天守の建設に関する技術的ドローイングがまとまって存在していることに言及し、これらが建設の責任者であった甲良宗広の手によるとみなしている。しかし、これらの図面は同族の甲良豊前により竣工図として建設後に描かれたものである(東京都立図書館, 2020)。いずれにせよ、これらの図面は江戸時代において、正確な投影図のような記述的な幾何学の高度な表現技術を職人が有していたことを示している。
一般に江戸時代の初期から中期においては、竣工図だけではなく、建築現場に縮尺図が存在していたが、それは極めて稀であり、たとえば畳の製造者に畳の敷き方を示すような一定の手仕事に特化した職人を補助するものであった。(註9 こうした図面の主な目的は、生産チェーンの内部における要求の伝達というよりも、説明の視覚化である。各々の大工棟梁の工房は秘伝書や雛型本や技術書と呼ばれた詳細図の記録を有していたが、それらは施工方法を伝えるものではなく、むしろ要素間のダイアグラム的な比例関係を言葉と寸法で記述するものだった (Coaldrake, 1990)。これらは各工房の秘伝とされ、建設の手引書に似たものとなっていた。実寸大の図面は精巧な木材の切り出しに用いられ、建設部材の生産のための実寸大ガイドラインの下書きの雛型となった。最後に、板図と呼ばれた木の板に描かれた図面(縮尺を有した技術的図面の希少な例)は木の部材の寸法や構成を定めていた(深井・戸樋口, 1996)。板図は全体計画のレイアウトを可視化し、大工棟梁が柱梁に必要な資材量を見積もることを助けた。
板図のような職人の手による 平面=投影型のドローイングは江戸中期にすでに存在していたことがわかっているが(註10、こうした方法が普及するのは江戸後期に木割術が発展する文脈においてのことである(Nakagawa 1986)。木材の部材取りに由来する木割術は、日本の木造建築において縮尺を固定しない比例体系として発展し、柱の太さと柱間の間隔の関係を基礎としていた。これは一定の要素の反復がより大きな全体を規定するという点で畳のモデュラー体系にも似ているが、より柔軟性が高く、構造要素とも関連しているという点で異なる。また、木割術は各工房で秘伝される手引書の成立にも関わっている。
15世紀頃に端を発する近代ヨーロッパの平面を投影する方法論とは異なり、日本の前近代の建設現場は建設をめぐる様々な実労働や手仕事を横断して意思を伝える統一的な媒介も、建設現場の外部から労働者に指令を伝える上意下達の統制も確立されていなかった。最終的な判断は職人のノウハウと経験に任されていた。建築家や技術者のような現場外のエージェントとして、最終的な仕上げを規定するための遠隔的な判断と規定の手段を有した存在はいなかった。これにより近代とは異なるかたちに権力関係が編成され、近代的な管理ツールによる典型的な上意下達の労働は生じなかった。この意味において、江戸時代の日本の建設現場の組織構造は、フローレンスのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の建設を通じてフィリッポ・ブルネレスキが結晶化させた変化がまだ起きていなかったヨーロッパ前近代のものと類似していた(Ferro 2010)。
しかし、日本における建設組織の制度化は、特権的な一族による知識・技術の独占と特化を伴いながら、職工たちの創造的自由への脅威の兆候を示し、江戸時代後期には職人仕事の自律性の衰退をもたらした。太田博太郎(太田 1947)によれば、木割術のような新しい投影技法に基づく労働従属化の新たな形態におけるノウハウの成熟は、創造性よりも効率性をもたらした。いずれにせよ、この過程は貫徹されず、前近代の生産様式の名残は1868年の明治維新以後もみられた。しかし明治維新から第二次世界大戦の間にも生産様式の変化は進行し、それまで木造軸組の構造に関連した職人技術が支配していた建設のありかたに煉瓦・コンクリート・鉄のような新たな素材や工業的プロセスが導入されていくことになる。
新たに登場した建築家と技術者(一般に建築現場とは離れた場所におり、建設部材の生産のための手工芸の技術を持たない)という地位とデザインの調停は、まったく新たなロジックを建設に挿入することになった。そして現場の外の一般的な専門知識を優先し、現場労働者の固有の技術や判断は、その熟練度に関わらず軽視するという、科学的・合理的アプローチの支配をもたらした。1868年の明治維新以前の建物を何であろうと「建築」として論じることや、どのような立場であろうと(大棟梁も含めた)建設従事者を「建築家」と呼ぶことは、日本の建設を語るうえでは時代と文脈を無視した解釈となってしまうのである。
近代黎明期(1868-1945)における生産様式:
建築と新技術の導入と馴致
この[19]世紀の終わりには、手の技術によって独占することができない新たな素材が登場した。すなわち、およそすべての近代建築史に示されているように、鉄と鉄筋コンクリートの登場である。これらは資本が機械の代わりに行使するようになった武器であり、建設のようにそれまでは近代工業によって手仕事を奪うことのできなかった領域において、現実の主従関係の代用品を確立した。これらの新たな素材は、かつては伝統的なノウハウに根差した手仕事を支えていた素材の地位を奪い、労働者たちを無力化した。…木と石は伝統的な技術を有した大工や石工とともに少しずつ建設現場から去っていき―これらは新たなかたちの支配にとっての障害物だった―その帰結として木と石の使用はモダニズムの最初の時代において暗黙に禁止されるようになったのである。
(Ferro 2018, 17)
江戸時代(1603-1867)の鎖国政策の撤回、1854年の開港、そして1868年の明治維新から始まる近代化に向けた諸改革の後、欧州と米国から導入された近代的な素材と技術に基づく新たな生産システムは建設という概念に不和を生じさせた。1868年から第二次世界大戦での敗戦までの転換期において、新たに輸入された「西洋的」なものとしての「建築」の概念と技術は、日本の地域的・歴史的な条件への適応(馴致)の過程を経ることになった。国外で過去四世紀にわたり発展した知識を日本は急速に取り入れた。政府主導の公共事業、および「西洋風」で施設を新設することを要求した国際的な重要人物たちの台頭(Stewart, 1981; Jackson, 2013) は、明治期の最初の三十年間に「建築」を日本に馴致させるための諸条件を創出した。
設計と様式は生産様式と並行して発展した。建築と工学の生産チェーンを基礎とする新たな建設ロジックは、それまでになかった専門家と素材と建設手法を要請した。この変遷は、近代化と通商の開始が新たな建設産業の発展や誘引を促し、それが新たな専門家と新たな素材を必要とし、さらには新たな技術の追求につながるという正の循環ということができる。ここで輪のように連なったすべての要素は、これらの変革のきっかけであり原因としてみなすことができる。
日本の近代化は当初から外国からの影響に大きく依存していた。1867年の鹿児島紡績所のような西洋的建築の応用にトーマス・ジェームス・ウォーターズのような外国人専門家がすでに関与していたが、お雇い外国人の政策は外国人専門家を政府が雇用するというより制度的な馴致過程のきっかけとなった。建築の分野では1874年から1880年の間に少なくとも13名の専門家がイギリス、フランス、プロセイン、イタリアから招聘され、そのひとりである英国人建築家ジョサイア・コンドルは帝国大学で1888年まで西洋建築を教えた(稲垣 1959, 36-43)。これに加え、新政府は先進的な工業技術を吸収するために1880年に学生たちをイギリス留学させており、その一団にはコンドルに師事した辰野金吾も含まれていた。三年間の留学後、辰野は1884年から帝国大学で教授として西洋建築の講義を受け持った(ibid.)。辰野の同僚の片山東熊は1886年にドイツに留学している(Steward 1981, 55-62)。両者ともに日本の建築家第一世代として数多くの作品を残した。
また、そうした煉瓦造の西洋建築の馴致に向けた国家主導の努力の外で、職人たちも新たな技術の発展に強い関心を示していた(Jackson 2013, 151-158)。この状況から生まれたものが擬洋風建築と呼ばれる様式・構造の両面における折衷主義であり、木造軸組構造や土壁のような日本伝来の技術が西洋の様式を模倣するために応用された。こうした様式的・構造的な折衷主義は棟梁や職人にとって自由に創造性を働かすことのできる場となり(稲垣 1959)、とりわけ装飾要素は「西洋風」建物を推進する国家方針と、在来の技術と、建設現場で利用可能な風土的な素材の合流点となった。
立石清重の実践は棟梁から(仕事の方法と建物の形態の両面において「西洋風」といえる)建築家に転じた顕著な例である。それまで長野で封建領主に仕えていた立石は、大工棟梁として城郭や社寺の建設に携わっていた(梅干野・他 2019, 947-952)。立石は横浜等の港で外国人が関与した建物を1872年に見学した後、独立して1876年の[旧]開智学校のような重要な作品を残した。立石の作品は一躍有名になり、1888年には造家学会に入会した。他にも市川代治郎や松木輝殷のような棟梁が擬洋風建築の推進者となった。これらの実践は木造軸組構造に基づいており、そのことが西洋的な形態を日本人による建設手法へと直に馴致させることを可能にした。
新たな設計様式を模索するための建築と工学の専門家の一団が、お雇い外国人の招聘から西洋化された日本の建築家たちの組織的育成によって進められたにもかかわらず、建築の生産様式は即座に新たな西洋式へと切り替わったわけではなかった。むしろ、19世紀終盤にかけては、従来の建設現場の職人の技術への依存が続いていた。コストの面から、こうした労働力が主に地域密着型であったこともその理由である。しかし20世紀になると、管理面での近代化も進み、幾千人もの棟梁や職人が従業員として組織化されていく。1891年には東京で1300人の建設従事者が東京でストライキを行い、日当の改善を要求したこと(かつ、その要求を通したこと)が記録されている(Obata 2018)。かつて棟梁が率いていた建設組織は封建的構造から資本主義的大企業へと推移した。その一例として、元来は寺社建設を専門としていた大工一族の14代目当主は1899年に神戸で竹中工務店を設立し、その後の数十年で日本の五大ゼネコンのひとつへと成長を遂げた。
より広範な生産様式の変遷と労働管理の強化はすぐに建設に異なる論理を要請することになった。製鉄産業は国営の八幡製鉄所が1896年に開設されたことで勢いを増した。鉄の国内生産は1901年の49.147トンから1913年の240,363トンへと増加し、この期間で鉄の輸入量も6,033トンから254,952トンへと急増している(Shimizu 2010)。1911年時点では八幡製鉄所で生産された鉄(当時の国内生産量の89%)の2.5%(670,541トンのうちの17,134トン)だけが建設産業に用いられたが、産業の躍進はあらゆる需要への対応準備が進んでいることを示している。同様に、セメントも当初は国営事業として1875年に国内生産が始まったが、1883年には民営化されている(Otaka 1963)。1888年から1911年でセメントの国内生産は2万トンから60万トンと30倍になり、1926年にはさらに300万トンに達している(Shimoda 2016)。
19世紀後期の日本の「西洋化」過程においては、1872年の銀座大火からの復興計画に見られるように、煉瓦造が主流であったが、一連の震災をきっかけとして鉄とコンクリートへの推移が生じた。1891年の濃尾地震は煉瓦造につきものの震災リスクを意識させ、鉄骨造の導入検討を促した。1906年のサンフランシスコ大地震は佐野利器などの日本の技術者の関心を捉えた。同年にこれらの技術者はサンフランシスコを視察し、建物の震災被害を工法ごとに比較し、鉄骨造と鉄筋コンクリートこそが耐震・耐火・耐久を同時に満たす日本に最も適した工法であるという確信を得た(Inagaki 1959)。1923年の関東大震災で浅草凌雲閣などの煉瓦造の建物の多くが倒壊した後、鉄骨と鉄筋コンクリートという技術的選択は大規模に適用されていく。震災後の鉄筋コンクリート造の建築は面積にして1927年には330万㎡、1935年には1,000万㎡にも増加した(ibid.)。全国的には木造軸組がまだ主流だったものの、これらの数字はコンクリート産業の安定的な成長を示している。
建設の近代化を促すこれらの政治的、経済的、技術的な圧力に加えて、1923年の震災は今和次郎と弟子の吉田謙吉が「考現学」の名において進めた手広い調査に記録されたように、近代化への文化的衝動を加速させていた (Kon and Yoshida 1931)。モボやモガのような新たな都市的な人物像に体現されたような大正時代(1912-1926)のモダンな生活様式はメディアによって大々的に宣伝され、西洋的な住宅の新たな空間の生産を促進した。明治・大正時代に発展した文化・経済の近代化に煽られた新たな(そして急速な)建設の需要は、東京のような大都市における生産様式を(主に西洋的な様式の建築の)工業的・科学的な生産へと推移させていった。
このように社会制度や文化に関わる理由に後押しされながら、台頭しつつあった工業経済における新たな素材と技術は、建築の構造的な安定性と必要資源の適切な利用という面においてコスト効率の合理化を要請した。木造の体系と異なり、建設部材のほとんどが建設現場で調達できなくなり、その生産にも管理された工業的プロセスが求められるようになった。親方や職人による生産様式への新たな素材とそれに伴う制度の導入は、実践的知識に基づく意思決定の余地を狭め、建設現場における意思決定者の立場を最小化し、技術的図面による集権化された規範的な設計過程において棟梁の仕事を管理することへの大きな跳躍となった。
日本においては布野修一(布野 1981)が、ヨーロッパにおいてはフェルロ(Ferro 2018)が指摘するように、鉄骨建設のロジックは木軸に近いもので、建設現場における組み立てや半剛接合のジョイントと熟練労働に依拠する構造的強度(とりわけ耐震強度)などがその類似点が挙げられる。しかし、鉄筋コンクリートの場合、型枠の事前の計画、鉄筋とセメントの比率の複雑な計算、要素間の鋼接合、劣った耐震強度、そしてなによりも、建設現場での一般には非熟練の労働集約といった要因が、まったく異なる建設現場の組織を要請した。コンクリートの造形性をより複雑かつ大胆に追求するほど、建設現場の外でなされる計算と作業がより重要となり、熟練労働者の直観的知識には頼ることのできない数学的モデルが新たに求められた。
したがって、木材から煉瓦から鉄とコンクリートへと向かう素材の推移は建築をめぐる思考の再編と、建設に関わるエージェントの新たなチェーンを要請し、とりわけ近代化以降は執務室で建築家と技術者が設計するプロジェクトに従属するものとなった棟梁の役割の変化は重要だった。しかし、19世紀までにヨーロッパで生じたことと概ね同様に、工業的な生産手段は新たな技術の潜在性を完全に使いこなすような究極のデザインを―生産機構とイデオロギーという側面において(マルクスの用語を用いれば下部構造と上部構造)―可能にはしなかったのである。古典的な意匠の模倣は新たに登場した技術とデザインのギャップを象徴するものであり、この状況はヨーロッパでは15世紀から19世紀に(Ferro 2021)、日本では明治維新から第二次世界大戦での敗戦までの期間に急速に生じたものである。
戦間期には建築意匠と近代化された生産チェーンの二元論を解決しようとする初期の試みがみられた。日本分離派(1920-1928)や創宇社建築会(1923-1931)などの初期の急進的な表現主義的運動がその例である。この時期に、国際様式と機能主義的運動の諸側面も日本において模索された。その例として、1920-30年代のノエミ&アントニン・レーモンドの作品や、1930年代の 石本喜久治、吉田鉄郎、山脇巌、山口文象、村野東吾、堀口捨己、土浦亀城 らの作品が挙げられる。前川國男 と坂倉順三はそれぞれ1928年と1930年からル・コルビジェに師事し、蔵田周忠はグロピウスの事務所で経験を積んでいた。1930年には政府も同潤会のような住宅団地や東京都内の学校等の設計に関わっている。
しかしながら、これらはまだ十分に発達しきっていない実験に留まり、これらの例外的な試みは特に1930年代以降はネオバロック様式や、コンクリートによる西洋の構造システムとヨーロッパ風の新古典主義と象徴的な日本式の屋根を組み合わせた帝冠様式のような折衷主義を推進した帝国主義的な政策の下で窒息していく。この傾向は1942年の「近代の超克」(Nakamori 2011, 2-30)のような論争の引き金となった。帝冠様式のような様式と、極めて国家主義的な文脈の只中でなされた政府公認の反近代的な議論がともに主流となり、このことが本来ならば不可欠であった建築意匠と工業生産の歩み寄りに軋轢と遅れを生んだ。戦争で破壊された都市の更地化が1945年と1946年になされた後、大きな犠牲を払った終戦とアメリカ主導の占領政策の司令部は、遅れをとった日本における近代建築に新たな発展の余地を与えた。
村松(Muramatsu 1959, 121-126)は明治期から敗戦までの建設産業の特徴を四つにまとめている。それらは(1)「封建的拘束および保護制度の解消」、(2)「請負業の成長・発展」、(3)「職人層内部の崩壊および再組織」、(4)「技術の変化」であり、この最後の変化において職人の技は時代錯誤となり、職人気質という言葉も「不合理と偏屈と時代遅れの代名詞」となったとされる。これらの圧力の高まりにも関わらず、戦後に「封建的」として問題視されることになるものも含めた、様々な労働組織の同時並存は戦後も特に地方において残されていた。江戸後期以降は階層的な労働組織が勢力をさらに拡大していったが、この階層構造の上から下までを技術的図面と建築家・技術者の仕事がついに貫通し、権力の集約と建設産業の全国化の前提条件が整えられるのは、戦後復興期のことであった。
1947年から1957年の建築論争の技術・建設をめぐる側面
急速な工業化(註11が進むなか、戦後復興への関与を深めることを目指して、複数の組織に分散していた日本の建築家たちは1947年に新日本建築家集団(NAU)として同盟を結んだ。NAUには浜口隆一や丹下健三や西山卯三や図師嘉彦や池辺陽のような若い世代の建築家や理論家が集った。この時期に展開した議論は近代建築論争(1947-1948)として知られるようになり(布野 1981, 128-156)、後の伝統論争(1953-1957)に先立ち、近代的デザインに基づく工業的手法と前近代的な建設の関係をめぐる論争を引き起こした。これらのふたつの論争はこの時代のイデオロギー的な問題となり、「伝統」という表現の多様な意味と形態の探求に導かれながら、日本在来の文化をさらなる変化のための旋回軸へと転じた。
浜口隆一の1947年の著書『ヒューマニズムの建築 日本近代建築の反省と展望』(註12はNAUのプラットフォームに枠組を与えた。機能主義的な近代建築とヒューマニズムを等式化することで、浜口は欧州モダニズムに由来する機能主義の原則を全面支持し、国家主義的な様式を批判し、いわゆるエリート主義的な古い様式に反対するものとして民衆に結びついた実践を提唱した(布野 1981, 128-156)。終戦直後の時代に浜口はヨーロッパ発の国際様式の手法を取り上げ、すべて近代以前にはなかった鉄とコンクリートとガラスを用いた「均一な性能」と「高度の技術水準」を伴う生産システムを基礎とした工業化を讃えた。マルクス主義の立場を強く代弁しながら、図師嘉彦と西山卯三は政治的急進主義者として浜口を批判し、工業的な生産諸力の発展は実際には階級間の格差を深めるものであり、外来の近代主義的な理想の導入は日本の建築にとって制約になると主張した(ibid.)。図師と西山の批判的立場はNAUのメンバー間では少数派に留まった。
浜口の主張を展開しながら、1948年に書かれたNAUのプログラム「行動網領」の三条は異なる建設形態の対立を強調し、「伝統」という言葉を、まだ前近代性と江戸時代の単純な代名詞ではあったが、明確に表舞台へと引き上げた(黒石, 2016)。
綱領三
建築界全般を掩う封建制と反動性を打破する。
一、建築生産組織、経営組織の近代化…
二、建築生産技術の機械工業化…
三、伝統の正しい批判及び摂取を基礎とする科学的民主的建築理論の確立 …
(NAU、行動綱領、一九四八年七月三日採択)(註13
この一節は「科学的」な建築と建設実践の「封建制」、すなわち建築=技術のワークフローと明治以前の労働組織の間の様々な不調和を示すものである。建設における「封建制」の継続は新たな建築の発展を妨げるものとみなされた。したがって「伝統」は近代の工業生産に内在化され、領有され、「摂取」されねばならないとされた。封建主義の克服を旗印として、NAUの行動網領は、近代建築が工業=経済チェーンなしには存在しえないことと、近代建築が旧来の生産プラットフォームという問題に直面していたことを明らかにした。いわゆる建設の「封建制」とは本稿で前述した生産様式、すなわち江戸時代における大名による資金提供から建設現場における職人の手仕事にいたる一連のものに関係している。
NAUの行動綱領は、それまで保守的な帝国主義・国家主義の美学に足止めされ、すでに遅れをとっていた日本の近代建築(稲垣 228-230)が、設計=平面と近代的生産様式のギャップの解消についに取り組み、生産組織の残滓を克服しようとしたものといえるだろう。NAUの活動的なメンバーであった丹下健三は「建設をめぐる諸問題」(丹下 1948)と題された論考で建設の「封建制」と新たな近代工業チェーンの関係性を探求した。当時は東京大学の助教授であった丹下は日本における「封建的資本」と建設行為のつながりを重点的に批判し、建設をめぐる生産の環がいかにして封建的特徴を近代においても存続させ、封建的組織がいかにして建設チェーンを支配してきたかを分析した。丹下は建築家が封建的構造に紐づいたあらゆる生産形態と対決することを呼びかけた。
…われわれ建設技術者は建設工業機構の封建制に遭遇しなければならなかった。これがわが國の民主化にとつて重要な阻止的な癌であり…これを一言をもつて云うならば、建設工業は尚まだ近代的産業資本のものではなく、封建的商業資本の支配にまかせられているという事實につきるであらう。所謂請負會社とは、古い封建的な親方關係によつて結びつけられた大工・左官・鳶職その他の職人組織をそのまゝのかたちで、封建的資本がそれを利用している形態であつて、底邊にそれらの近代的な組織をもつことのできない職人層を置き、その上に段階的にピラミッド形の支配形態をつくりあけ〔ママ〕、その内部の各頂點には、問屋的・高利貸的ボスが坐り、最後の頂點に所謂請負本社とゆう封建的資本が寄生しているところの組織である。…セメント工業、ガラス工業、製鐵工業など近代産業形態として発達して来たところの建設資材工業は、そのピラミッド系列のなかに存在することはできず、たゞそれらの製品がピラミッド系列のなかに入りくるところでは、常に封建的資本が介在し… (丹下 1948)
丹下は江戸時代末期において大工たちの組合が請負業や下請業を担っていたことを指摘した。日本最大級の五大請負会社(スーパーゼネコン)のうちの三つ(鹿島、清水、竹中)が大工同士の組合から生じたものであり(Clancey 2005)、丹下にとって、この体制は構想(設計の前身)と建設を一体的に行う近代以前のやりかたを引き継いだものだった。丹下はまた融資と負債の制度が、異なる階級間の封建的依存性の諸関係、とりわけ土地所有に対するアクセス管理をめぐる関係を覆い隠していることを指摘した。建設会社についても同様に、日本の四大財閥のうちの二つ(住友、三井)が江戸時代から続くものであり、建設の根底にある融資制度を財閥が動かしていることを指摘した。丹下は20世紀版へと更新された前近代以来の生産チェーンへと職人が囲い込まれたことを認識していたが、建設をめぐる諸問題の埋め合わせとなるものとしての近代産業に全幅の信頼も寄せていた。
丹下は江戸時代以来の生産様式と戦後の生産手段を連続的なものとしてみなす視点を創り出した。建設従事者は以前のシステムを模倣し、その利点を活用した。親方の率いる工房は明治維新後には建設業者へと姿を変え、棟梁たちは資本主義制度の内部に収まるよう実践を更新して、賃金労働者として大手請負業者へと吸収されていった。新たな建設資材は建築現場の外側からの厳密な指示としての技術的図面を通じた労働者管理のありかたを強制したという、本稿の第二部で検討され、フェルロの「武器としてのコンクリート」(2018)にも言及されていた考えは、丹下にとっては、近代建築のデザインと歩みを合わせた工業的な生産様式に向けた建設の進歩についての自身の主張を積極的に正当化するうえで重要なものとなった。丹下はここに自律性の喪失を見出す代わりに、この技術的転換が封建制を克服する仕組みとなると考えた。丹下にとって「封建的」とは上層が下層を搾取するピラミッド状の労働組織(「親方関係」)を意味していた。
1940年代の議論においては「建設」も「伝統」もまだ結論の出ていない主題であった。近代建築論争(1947-1948)と伝統論争(1953-1957)の間に、丹下は広島でのコンペ (1949)を勝ち取り、建築士法の成立(1950)に端を発する建築家という職能についての白熱した議論に参加した。近代文化と伝統の関係については、[美術家の]岡本太郎が、「みずゑ」1952年2月号に掲載した縄文土器についての記事を皮切りに(岡本, 1999)、縄文と弥生をめぐる重要な論考を発表していた。丹下は1952年には桂離宮を訪れ、1953年には伊勢神宮の式年遷宮を見学している(Cho 2012)。
NAUの行動要綱の三条にもみられた「伝統」と「建設」(数多くの様々な定義を含む)という主題は、川添登が「新建築」の編集者に就任した1953年5月以降、日本の近代主義者たちの議論に深く絡み合うようになっていた。川添は当時行き詰っていた国際様式的な機能主義に代わる新たな方針として「伝統」を検証する意図を1953年7月の編集後記で「住宅は人人〔ママ〕の生活と結びつき、そして人人の生活は、長い日本の傳統の上に立つている。…近代機能主義は古きものへの闘いから生れ、そして育つて来た。しかし、古きものは全て惡とする思想は過去のものとなつた。」と表明していた(川添 1953)。しかし、同年11月に、これ以降の議論の枠組を設定し、建設をめぐる問題を再び問う西山卯三の論考を掲載するまでは状況は静かなままだった。1940年代後半には浜口隆一・池辺陽・丹下健三を筆頭とする近代建築家の一団とは対極的な立場をとっていた西山宇三は、建築家が民衆のための住宅を普遍的に供給するための方法を提案するために「…昔なら大工まかせになつていたもの[住宅設計]が、今では大部分がいかがわしい住宅會社にながれこんでいる」と日本の歴史的遺産についての概観を述べた(西山 1953, 63-71)。
西山にとっての「伝統」は、寺社や(桂離宮などの)皇宮のような過去の偉大な建築ではなく、京都のような市街地の木造都市住宅を建設するための平凡な技術から立ち現れるものであった。西山は「都市の借家建築に代表される大多數の木造建築、これは…日本人の生活に密着しているという點で、また過去の建築技術のさまざまな遺産をもつとも現代的に集積継承しているという意味で…もっとも「日本的」なものだといえよう」と主張した。したがって、近代建築の教義の押し付けは日本的な需要から外れるものであり、鉄筋コンクリートなどの技術に直接言及はしなかったものの、機能主義的の諸原理を批判した。(註14 西山の狙いは、多義的な「機能」の代わりに市井の人々の「生活」を論じることで、フィールドサーヴェイによって常に住人との関係において新たな住宅を分析し、安価な技術を活用した計画手法を提案することであり、これは日本の地域的な条件や建設文化との対応において木造軸組工法を意味していた。
日本に近代建築を普及させるための主導的な試みを率いていた丹下や川添にとっては西山の立場はおそらくは望ましいものではなく、西山への回答はそれから入念に用意されたとみられる。丹下は国立国会書館のための競技設計案についての「伝統の近代化と民衆に奉仕するプラン」と題される短い記事で「丁度古くからの工匠が喜びをもつて木に自らの手を下していたように、型枠の職人もコンクリート打ちの職方もこのようなコンクリート打の仕事に対しては工作の喜びを見出だしているところを見て、私たちは日本の建築にとつて、機械と並んで人間の手が、建築を芸術にするために捨て去ることのできないものであることを確信するのである」(丹下 1954, 25)と記し、伝統を近代建築へと摂取するアイデアを実践に移している。丹下はコンクリートの型枠づくりに棟梁の手仕事の技巧を再び挿入することを提案したのだ。ひとたび建設が終われば取り去られ、幽霊のようにしか存在しえない建築要素である型枠が選ばれたのは皮肉なことである。
これらの前身的な議論が集約したのが1955年1月である。新たな建設技術への転回を推進する近代主義的な機能主義に抗う西山の挑戦に対するより体系的な反応は、「新建築」1955年1月号に掲載された一連の記事[岩田、丹下、宮川]に見ることができる。西山の立場は、国際共産主義運動という西山の政治的視点と、つねに現実を検証しようとする意志に基づいて、社会主義リアリズムの名において論じられた。(註15 この当時まだ「伝統論争」という名前が正式に与えられたことはなかったが、1953年の川添の編集後記、同年の西山の論考、および「新建築」1955年1月号のいずれもこの論争の引き金として考えることができる。「新建築」1955年8月号の編集後記は伝統をめぐる一連の記事を「伝統論議」として参照していたが、1950年代の「新建築」紙面上には「伝統論争」という言葉は見あたらない。1950年代の「新建築」紙面のこれらの議論を包括する「伝統論争」という用語は藤岡洋保(藤岡 1991)やその後の藤森照信 (藤森 1995)の論考に見られるものである。
一般に伝統論争の発端される丹下(丹下 1955a, 15-18)の1955年の論考「現在日本において近代建築をいかに理解するか―伝統の創造のために―」のなかで、丹下は戦後日本には旧来の生活様式になお拘泥し、進歩に対して懐疑的な人々がいると考えた。この問題を克服するために、丹下は建築表現([精神性とは区別されるものとしての]形態の美に相当するものであり、「人の肉体を心地よくさせ、目を見はらせ、そうして精神をゆすぶるもの」)に取り組むことを提案し、それが近代建築のための新たな伝統を創出するための「近代的なものと伝統的なものの交錯」を可能にすると論じた。つまり、(丹下が1954年の記事で示したように)大工職人の熟達した技巧をコンクリート型枠づくりに用いるような方法で、古いものと新しいものを混合することで、丹下は既存の伝統を克服する新たな伝統を、文化的にも建設的にも、創出することを提唱したのである。ル・コルビジェに師事した最初の日本人である前川國男は、こうした伝統論の前身として、すでに1942年にヘーゲル的な弁証法を暗示しながら伝統という概念を動的な創造へと新たに枠づけていたが (註16、1950年代の日本の建築家間の議論という文脈においては、「伝統」が創造として、すなわち与えられた過去の事実や物質的な遺物を参照するものではなく歴史を解釈するものとして建築家や歴史家の間で広く論じられたきっかけは、丹下によるこの論考がきっかけであった。
丹下(丹下 1955a, 17)は同じ論考のなかで、執筆の数年前に前川國男とともに訪れたマルセイユのユニテ・ダビタシオンの建設現場で遭遇した二項対立と、近代主義者が教条とする諸前提をめぐる驚きを報告している。そこで丹下と前川が目にしたのは期待されていた「機械で作られたものがもっている均一、正確、小ぎれいさ」ではなく、「手でこねあげたような粗放さ」でしかなかった。丹下はここに「危険」が横たわっていると考え、それを「この6年のあいだ、おそらくコルビジェのなかでは『機械』と『手』で表徴される、ヨーロッパの頭脳と感性の、進歩と伝統との葛藤が行われてきたにちがいない。…機械による技術的前進から、手による感性的直観へ、それは今一歩で伝統への観念的後退なのである。」と表現した。技術的発展の段階は、機械と手の相互作用の性質を定義するものとみなされた。丹下はニューヨークのような都市について「機械の無限の力が、やはり近代建築を創造しつづける力ではないだろうか」という見解を示して、この問題が克服されていると考えた。ル・コルビジェの建設現場の見学で丹下が覚えた「危険」は、生産諸力の進歩は手仕事の(抑圧とまではいわなくとも)最小化を導くことができるという丹下が工業技術の発展に抱いていた確信を明らかにした。同じ「新建築」1955年1月号で、川添は岩田知夫のペンネームで丹下が1954年に広島の設計協議に寄せた次の言葉を引用している(岩田 1955, 62-69)。
…このときも、私たちと一緒に差物大工が50分の1の木の模型を作つては、こわして並行して進めてくれた陳列館が競技設計のときから變つてきたのは、何か感じとして、わたくしの頭の中にプロトタイプがしだいに強く現れてきたためのように思われる。言つてみれば、廃墟のなかから立上つてくる力強いものをコンクリートを頼りにして創つてみたかつたのだと言えるであろう。(丹下・浅田・大谷1954, 12-13)
丹下のこの証言は、コンクリートで造られることが前提となっている建物の設計実践へと熟練の大工の手による木のモデルが組み入れられたことを示しており、ここでは尺度を有した木軸による手仕事の創造が、工業的プロセスに結びついた鉄筋コンクリートへと推移させられている。木製モデルの制作は建築において一般的にみられるものだが、ここでは設計段階において熟練の大工を起用して単なるプレゼンテーションのための模型以上のものをつくり、建築事務所の内部において職人の(木に依存した)技巧をコンクリートのために取り入れているということが注目に値する。この論考で岩田は丹下の広島のプロジェクトを分析し、たとえば1954年の清水市庁舎のような丹下のその後の作品の展開を、広島のプロジェクトの形態には潜在していた民衆の力と矛盾するものとして批判した。伝統論争をめぐる通説とは異なり、1955年のこれらの初期の議論においては縄文と弥生の様式的対立は言及されていない。
丹下が創造としての伝統という考えによって伝統との調停を追求していた一方で、池辺陽は近代建築の機能主義の急進的な擁護者としてこの論争に登場し、西山と明確に対立するかたちで工業的手法を礼賛した。東京大学の助教授であった池辺は吉村順三や清家清などの建築家たちによる「日本的デザイン」を利用した作品を攻撃し、それまでの生産様式からの決定的な離脱を伴う新たな創造としての「伝統」という考え方を推進した(池辺 1955a, 41-43)。さらに池辺はイサムノグチやジョージ・ナカシマなどの外国における実践にも批判的に言及した。池辺にとっては「伝統はよりかるもの、堀り出すものではなくて、私たちの闘う相手」であり、現代生活のなかで新たな伝統を追求するために批判されるべき対象だった。この論考に表された激烈な怒りに応じて、「新建築」の編集部は丹下研究室、MIDOグループ、UHONグループ、RIAグループ、清家清研究室の5つの研究グループに回答を要求した。そのうち、丹下研究室とUHONグループは建設という話題を直接的に扱っている。
沖種郎を文責とする丹下研究室の回答(丹下 1955b, 44)は、職工的生産を近代的生産、とりわけ、建材(畳等)の標準化と互換性へと統合することを提案した。そこでは「手工業的生産の中で育つた職人技術は、現代におけるクラフトマンとしての正当な地位を獲得する事によつて、単に打放しコンクリートの中だけではなく、フィニッシュの分野にひろく生き続けなければならない」として、労働を馴致する過程を必然的に伴うものとされた。注意すべきは、前近代から近代への流れのなかで、職人はもはや漢字の「職人」ではなく外来の言葉や概念を示すカタカナの「クラフトマン」と記されていたことである。さらには丹下周辺の学術的サークル内で拡張された「伝統」概念が提示され、それは建設技術を馴致するという提案に対応するものとして用いられた。すなわち、「過去の遺産が、私たちの現在及び将来となんらかの関わりをもつとしたら、それはどのような意味をもつているのだろうか…それはまず私達現代の“眼”で濾過されなければならない。同時にそれは制作の過程を通して、より新たなものとして創られ息吹かねばならない。…このように遺産が受けつがれ、現代のものとして生かされた時に、それが初めて“伝統”といわれるのであつて、それは絶えず生成の過程の中にある動的なものであるといえよう。」(Ibid., 44)
池辺はこの論争に四か月後に再び参加した。近代以前に生産された建築を賞賛しつつも、池辺はそうした素晴らしい建物の建設をかつて許してきた条件を現代社会においては更新しなければならないと主張する。前近代の建設技術も、それを生み出した社会的需要も、もはや現代社会の要請に応えるものではなくなっているというのが池辺の立場である。
私たちが古典建築を見る時それに打たれるのはなぜだろうか。プロポーションの美しさ、ディティール処理の巧みさ、を問題にする人もあろう。又全体の構成をいう人もあろう。しかし私はそれらすべてを駆使した建築家の個性、又それを生み出した社会、技術を思わずにはいられない。古典建築はその時代の技術、社会の力を建築家が最高度に出し得た時にその力が私たちを打つのではないだろうか。…社会、技術、等の立場から考えてゆく時、和風建築はそのままでは現代の生活に適合しないのは明か〔ママ〕である。和風建築によつて支えられる生活は特殊な階級・生活にすぎない。そのことはこれらの多くが現在料亭や旅館、一部の富裕階級のためにのみつくられていることからも示されている。(池辺 1955b, 66-69)
川添登、丹下健三、大高正人、吉村順三、コンラッド・ワックスマンが参加した討論では、池辺は自身の立場をさらに明確に表明し、異なる時代の生産諸様式との関連において議論を展開した。
江戸時代から明治にかけての日本の歴史、或いはそれが建築に与えた影響というものが、現代でもまだ拭い去ることができないで、われわれの考え方に特殊な影響をもつているのではないか。…私は自分自身の建築の仕事の中で、江戸的なものをいかにして拭い去るか、同時に江戸時代と明治時代はあまり変りがないし、現代も変りはないと感ずるのです。…江戸的な手工業の建築というか、もつと広い人間の手工法というものは、徹底的に現在のわれわれ日本人から何かクリエーションに対する欠くべからざるものを喪失させているのではないか (丹下・他1956, 73)
このように池辺は過去の歴史に抗う立場をとり、日本の文化と生産になおも存続するこれらの江戸時代の残滓が近代建築の制約になっているという考えを表明した。丹下と比べても、池辺は前近代的な生産様式に対してより急進的な立場をとっている。池辺は日本的な様式的要素に関連づけられた前近代の生産手段の痕跡を完全に一掃することを求めたが、丹下はそれを新たな近代的な建築形態へと馴致させることを求めた。
伝統論争と並行して、丹下は香川県庁舎(1954-1958)などの様々なプロジェクトを進めていた。これらの作品において、丹下は伝統を技術的・生産的な意味で消化するという作戦を実践に移していた。丹下は木造建築の構造をコンクリートで模倣し、一般的な木造よりも遥かに広いスパンを獲得しつつも、1868年の明治維新以前に寺社建築で行われていたような独立構成要素からなる組み立て原理を用いた。しかし、これらの要素はここでは先進的な強化技術を用いた現場打ちのコンクリ―トで実現されたのである。このプロジェクトは丹下の模索をコンクリートの造形性と有機的形態へと最小化したものであり、直線的な建築要素を反復的に用いていた。
四世紀以上も前に実践されたイタリアのマニエリスムにも似たやりかたで、丹下は様式の転用および意匠と技術の分離を示すディティールを挿入した。たとえばコンクリートの支柱は木造であれば水の影響によるメンテナンスを軽減するための後退した幅木を有しており、梁は柱に接するように外向きに複製されて分離した要素同士の連結を模倣し、コンクリートのレーリングとしてデザインされた梁は角と交わり、独立性を偽っていた。概して、香川県市庁舎は伝統論争における丹下の理論的アイデアから建設されたマニフェストだと考えることができる。しかしこの木造技術のコンクリートへの形態的流用は、浜口隆一(浜口 1955, 13-14)が前川国男・坂倉順三・吉村順三の設計よる国際文化会館の分析において「戦後最大のジャポニカ」としてすでに皮肉めいた批判をしていた手法でもあった。浜口は前近代的な形態を近代建築にそのまま直接用いることに懐疑的であり、こうした手法は近代建築家たちの間でジャポニカという言葉で批判的に言及されていた。(註17

Fig.1 丹下健三の設計による香川県庁舎 (計画1954-竣工1958)のディティール
撮影:ガブリエル・コーガン
香川県庁舎に見られるこうした木造形態のコンクリート造への馴致は、丹下による自己批判の契機を含んでもいた。なぜなら、丹下が作品を通じて追求していた技術的な発展は、十分な技術を持たない労働者の登場や失業の増加といった労働をめぐる諸関係に混乱をもたらしかねないことも認識されていたからである(丹下 1956a, 73-84)。丹下は「かくしてわれわれの理論は技術の蓄積性を否定するものであつてはならず、いかにして技術の当面する矛盾を克服するかという実践的な展望をふくまねばならない。」としながらも、その点について「建設の合理化と労働者の失業問題は常に表裏の関係にあるのであつてこれを形式論理的に考えるかぎりわれわれはそのいずれに向うべきかという結論は出ない」と態度を決めかねていた。
丹下の包括的で最も力強い見解を示しているのは「新建築」1956年6月号に掲載された「現代建築の創造と日本建築の伝統」(丹下 1956b, 29-37)である。この論考で丹下は建築技術と歴史的議論を接続し、「伝統」についての見解を明確に整理し、「過去と未来とを創造的に橋かける」任務を支持した。ここには建設現場における近代主義と伝統の齟齬を調停するための丹下の修辞的な策略が横たわっている。型枠職人の技術についての言葉にすでに示されていたように、丹下は「精神」(1955a)や「内部」(1956b)に存在する伝統に関心を向けており、それらは作品の形態に表出していなくても構わず、前近代のノウハウの再評価と近代建築への消化もその対象に含まれた。1950年代を通じて丹下の建築家としての実績が高まっていくなかで、丹下の経済的批判の対象は建設会社と高利貸しから建設現場における建築実践へと推移した。丹下は、千年以上にわたる日本の建設手法は技術的発展に対して保守的であり、近代の産業/文化はこの状況を克服しなければならないと主張した。
アジア大陸の仏教の影響下に, 法隆寺・東大寺などの歴史的遺産が建設されたが、大陸からの技術的成果も、横に広がってゆくことなく, 仏寺の建築に適用されるだけに止つた。この技術の停滞は、生産力の絶対的低さや, 富の蓄積の貧しさからくるものであるとしても、しかしそれはまた、日本人のこの現実認識における情意性や, 自然認識における消極性といつた弱い姿勢からきている ものであって、ただ木に頼るという技術的態度は, 近代にいたる永い世紀のあいだ繰り返され、その間に、土や石を開拓するという試みは一度も行われなかったのである。建築の技術の歴史は、空間を克服する基本であるスパンする技術との 格闘の歴史であるが、日本では伊勢によつて獲得された柱梁というもつとも素朴な形式を決して発展させることがなく、アーチ、ボールト、トラスへの発展は全くなかつたのである。この技術の停滞は、 生活の多様な展開に対応してゆくことができなかつたのである。(丹下 1956b, 31)
技術的な創意工夫の不足を問題視しながら、丹下は設計者=建築家の立場から熟練技術者に対して異例の批判を行い、職人たちのノウハウを標的にした。丹下の言説は、親方関係に基づく伝統的な労働組織を一掃し、それにより(国内外の資本に融資された)建設の工業化の科学的正確性を推進することを目指していた。丹下の実作が実証したように、鉄筋コンクリートそのものがこの転換を推進するための根本的な要素となった。すなわち、素材の変化は、新たな経済産業の発展を通じて、労働の論理の変化を可能にしたのである。
丹下の言説の根底にあったものは「日本の建築家―その内部の現実と外部の現実―」(丹下 1956c, 7-13)で表面化した。丹下は建築家の役割と現代の生産諸力についての分析を通じて、「日本の場合について、結論的にいうならば、こういってもよいであろう。この対決の場面において、[建築家は]一方には強い封建的な勢力の残渣, 権力や権威に遭遇」するとして、建設業における封建主義の残渣を検討することで障害の克服を目指した。この観察に基づきヨーロッパの事例を参照することで、丹下は日本における建築家の役割の歴史的成立過程の分析とその様々な障害についての議論を展開し、現代日本でこれを体現するものとして、棟梁的な役割の永続化と、借入制度と四大財閥の影響下にある巨大な建設会社を挙げた。ここでは丹下がかつて「建設工業機構の封建制」や「わが國の民主化にとって重要な阻止的な癌」と呼んだものがより正確に説明されている。
すでにヨーロッパでは、古代社会において建築家層が現われている.しかし、これについて触れることは、私にはできない.むしろそれが、封建中世にいたって、建築家的存在が、建築職人層のマスター、あるいは棟梁的なものになってゆき、そのように、一応還元されたところから再び近代的意味の建築家が登場してくるという点に注目したいのである….[日本における]クライアント、建築家、施工者の分化は、ヨーロッパ世界に比べるならば、不十分にしか成熟しえなかったような歴史的条件があったように思われる。…日本の封建社会における大工または棟梁は、自ら設計をし、また自ら施工をしていた.そうして現在でも棟梁または大工の設計施工による建築は多いのである.そうして、施工が請負という商業的企業形態をとったあとも、設計と施工の分離分化は進展しないままであった.現在の請負企業にはほとんど設計部門が従属しており、とくに大企業においては一般建築事務所の匹敵することのできないほどの大規模な設計組織が存在しているということは、日本の特殊性であり、また日本の歴史的過程から説明しうるものであるかもしれない。…日本の歴史のうえで、西欧的な意味の建築家、いわゆる自由なる建築家は、辰野金吾にはじまるといってよいであろう.今から70年ばかり前のことである.しかし、日本の社会は封建的な社会から市民社会を経過することなく、資本主義社会につきすすんでいたのであり、…彼の建築家としての立場、またその意識には、ときの権力にたいして、また施工者にたいして、毅然たるものがあったといわれている.しかしその背景をなす市民意識は、日本には成熟していなかったのである.当時、…建築家の設計を必要とするような建築は、国家資本か、あるいは財閥によるものであって、一般国民のものは、ほとんど棟梁か大工まかせであったという事情からみて、当然のことであろう、それはまた、日本に市民社会を成熟させなかった社会的条件と、うらはらのものなのである。(丹下 1956c, 9-10)
丹下はここで二面的な問題を扱っている。ひとつめの側面は建設における生産制度の発展が独占的資本主義に歩調を合わせていたことである。もうひとつの側面は職人の手仕事および棟梁による現場管理に基づく生産制度の残渣であった。1950年代に近代建築の完全な発展が生じるかどうかは、丹下の見解によれば、この二面的問題の克服にかかっていた。さらに、この歴史分析のなかで専門分野としての建築が強いてきた概念的な変化について抗いながら、丹下が「建築職人」という前近代には存在していなかった職能を表す新語を創り出したことに注目してよい。
生産様式をめぐる議論と並行して、丹下は岡本太郎が先だって対置させていた縄文と弥生の土器の美学的・政治的な二元性を議論に再挿入した(丹下 1956b)。伝統論争についての後世の研究ではこの論点が主要な側面とされている。(註18 1952年に、岡本太郎は美術雑誌「みづゑ」で縄文時代(諸説あるが紀元前14,000 – 300年頃)の先史時代の土器について論じた。炎にも似た表面と形態の不規則な物質性を持つ縄文土器は、食糧不足や自然の脅威に直面していた当時の人々の生活環境とつながった力強く直感的な表現性を有するものとされた。岡本は縄文土器と、その後に続く、貴族的農耕社会が成立した弥生時代(諸説あるが紀元前4世紀から紀元後3世紀頃)の土器のそれぞれの美学を対立構造において論じる枠組みを確立した。縄文の凹凸に富み、何かに抗おうとする力強さに対して、弥生土器は節度を保ち、簡素で、洗練された外見を有していた。この対立に岡本は政治的な価値を挿入した。すなわち、縄文的なものは民衆の力を、弥生的なものは支配階級の洗練に基づく階層化された不公平な社会を、それぞれ象徴するものとされたのである。
この美学=イデオロギー的な縄文と弥生の対立軸は、後世の解釈では伝統論争を象徴するものとして度々扱われるようになったが(藤森1955)、建築の伝統論争の文脈においては1956年後半になるまでは歴史家の渡辺保忠の論考(渡辺1955)で一度だけ言及されたに過ぎず、それ以降も議論における二次的な主張に留まっていた。丹下(丹下 1956b)は縄文時代の竪穴を農家に、弥生時代の切妻の高床式を貴族政治にそれぞれ関連させることで岡本の理論を導入した。丹下の見解においては、縄文的なものは自然の諸力を支配しようとする意志を象徴するものの、弥生も含めたその後の展開において、この意思は平安時代のもののあわれや江戸時代の侘び寂びといった美学的価値のような、人間をとりまく自然条件の消極的な受容へと次第に発展してゆく日本固有の弱さを克服できなかったとされる。
軒や障子といった伝統的形態に込められた創造的精神を認めつつも、丹下はそれらを「技術史的停滞 のなかで形式化された方法」(丹下 1956b, 37)として批判し、美学的な問いを近代技術による新たな創造として技術的な問いへと翻訳することで、自然を科学技術的に支配しようとする西洋的な態度と対置される日本の「主情的な自然主義」に抗った。こうして丹下は「日本の伝統のなかに流れつづけている創造の姿勢と、それにまとわりついている表現には、私たちが克服し、否定し去らなければならないものを多くもつている。このような消極的姿勢を克服し、否定することによつてはじめて日本の伝統のなかに獲得された方法、あるいは方法的成果を、創造的に継承してゆくことができるのである」(ibid, 36)と宣言する。しかしながら、その二か月後、丹下の明確に技術論的な主張は、白井晟一の「縄文的なるもの」(白井 1956, 4)によって美学的=イデオロギー的な言語へと引き戻されてしまった。白井の論考は歴史的な連続性を有した創造のための想像力のふさわしい源として縄文的なものを称揚し、貴族文化としての弥生と対置した。こうして生まれた縄文/弥生という一種の様式的=美学的=イデオロギー的な対立軸は丹下の建設技術をめぐる議論の焦点をぼかしてしまい、縄文か弥生かというこの表面上の選択は、実質的には、鉄とコンクリートに関連した生産諸力というこの時代に生まれつつあった同一の下部構造を等しく肯定するものとなった。
後世の研究者 (例として塩原 2022; 藤森 1995; Lin 2010)が一般に重視する側面とはうらはらに、伝統論争は当初は縄文/弥生の美学的=政治的な対立ではなく、主として、日本人にとってはまだ相対的に新しく異質なものであった鉄とコンクリートを文化的に文脈づけ、これらの素材とそれにまつわる技術を日本の「伝統」という歴史的連続性へと接続する試みとして始まったのである。縄文と弥生は1956年半ば以降に現れる後期の論点であり、ある意味では、一連の論争を結論と崩壊に導くものだった。本稿の予備調査において、1953年から1957年に「新建築」誌上で伝統という主題を扱ったものとみなせる約50の論考のうち27事例が議論の本質的な主軸として技術や建設を論じていたことがわかった。一方で、縄文と弥生の様式を直接論じている記事はわずか6事例だった。(註19 技術や素材や建設を論じた論考のうち、本稿のなかでは扱っていないものには、川添登 (川添 1955)、ワックスマン (Wachsmann 1956)、山本学治 (山本 1956)、葉山一夫 (葉山 1956a)、浜口隆一 (浜口 1956)によるものがある。
1956年半ば以降に様式とそれに関連するイデオロギー的なメッセージとしての縄文/弥生の観念的な選択として脱物質化していた伝統論争の水面下で、あまり目立たないものの、建設の問題を扱う現実主義・物質主義的な議論も1956年2月に端を発するかたちで展開をみせていた。福島教育会館のプロジェクトを中心としたMIDOグループの大高正人や足立光章や鬼頭梓や木村俊彦らの論考(大高1956, 20-21; 足立1956, 21-22; 鬼頭・木村 1956, 23-24)は、コンクリートによる建設に地元住民のコミュニティを関与させ、近代の建設技法をオープンテクノロジーとして地域化する試みを論じた。後にこの試みは葉山一夫により「建築創造におけるリアリズムの方法」として理論的に整理され(葉山 1956b, 30-33)(註20、新たな技術と既存の社会=経済的構造の遭遇というこの当時に展開していた物質的条件へと埋め込まれた。しかしながら、この民主主義的なコンクリート建設へのアプローチは後につづくものを見つけることができず、その後の高度成長期において主流となる鉄骨とコンクリートによる建設へと、理論的にも実践的にも、道を譲ることになった。最終的にできあがるものの様式的な方向性(例:縄文、弥生)からだけではなく、人々が建設に関与する(しうる)方法そのものから近代的な生産資源と人々の暮らしを調停しようとしたMIDO同人らの努力にもかかわらず、それは伝統論争においては破調的なひとつの立場に留まったのである。
伝統論争についての今日の主流の見解(例として Lin 2010, 40)は、縄文と弥生をめぐる論争がそれ以降の丹下の美学に影響を与え、その後の作品において流麗なミース的・弥生的な構造から重厚な縄文的形態への移行を導いたと主張する。この点について本稿は、設計と建設の関係改善、生産手法の発展、そして技術と「伝統」の関係の入念な検討こそが、伝統論争直後の丹下に鉄筋コンクリートの造形性の潜在力を十全に活用することを可能にしたと主張したい。(註21 「伝統」を摂取するためにコンクリートによって木造建築と職人技術を率直に模倣した移行的な時代(香川県庁舎, 1954-1958)のあと、丹下はコンクリートという新素材のなかに自身の「表現」を自在に生産できることを発見し(戸塚カントリークラブハウス, 1960-1961)、「伝統」はもはや形態ではなく生産手段そのもの(労働力や、型枠工に転身した職人など)として摂取されるようになった。興味深いことに、新たな生産様式によって様々な意匠を模倣するという1950年代の丹下の方策は、(帝冠様式のような)1930年代の諸様式に用いられた手法に近似している。いずれにせよ、伝統論争を通じて丹下の作品が導いた形態と言説と技術的発展は、それ以降の期間において、新たな生産手段への設計行為そのものの導入に可能にしたのである。
伝統論争を締めくくる言葉と、縄文/弥生の二項対立と生産様式をめぐる議論の合流は、芦刈図というペンネームで掲載された読者投書というかたちで訪れた(芦刈 1957, 73-75) (註22。この人物の正体は本稿の調査では特定に至らなかった。この投書は縄文と弥生の対立軸を「“ガラス張り” 流行でほくほくのガラス会社の景気にあわてたセメント会社の必死の攻勢が始まったのであると。 “逞しい” 壁や柱はセメント量の増大を意味する。オート・メーションに近い大セメント工場が続々と完成しているではないか」と揶揄し、縄文の重厚性はコンクリート産業によって実体化され、弥生の洗練と軽やかさはガラス産業を満足させるものであると論じ、「“弥生と縄文の葛藤” という交替現象に終らせないためにも十分な手続きをとらなくてはならない。ショート・スカートからロング・スカートへの変転よりも、その社会的責任はひとまわり大きいのである。…そうでないと “ガラス屋とセメント屋の葛藤” に終るであろう」(ibid, 73)と警告した。まさにこの投書の題名「“縄文”論議の観念化を防ごう」が示すように、芦刈はわずか数行で、縄文と弥生の様式的な二項対立のなかで急速に生じていた下部構造(生産機構)と上部構造(イデオロギー)の分離を橋渡しした。建設をめぐる物質的な現実を再び議論の場に戻すことで、この小さな抵抗は、伝統論争の発端が近代の生産諸力と人々の生活をよりよく調停する方法をめぐる、複雑に絡み合う技術=文化的かつ物質=記号的な問いであったことを思い出させてくれる。しかし、もはやこのような生産との関連において伝統が論じられることはなくなり、川添登は早くも1958年にその帰結を「<民衆>を欠いた<機械>と<民族>の結合」と断じた (川添 1958, 135)。

Fig.2 丹下健三の設計による香川県庁舎 (計画1954-竣工1958)のディティール
撮影:ガブリエル・コーガン
結語
日本における前近代、とりわけ江戸時代の生産手段の特徴に基づき、本稿は1868年の明治維新以降の西洋的な建築にまつわる工業技術の導入が、次第に建設労働の組織をより階層的で機械化された制度へと再編し、建設現場の裁量を狭めてきたことを示した。19世紀後半には、日本はノウハウと技術を輸入するだけではなく、セメントや鉄といった新たな建設素材を生産する国家産業の開発を始めた。この時期における生産様式をめぐる様々な変化にも関わらず、(それまでは大工や棟梁による木を用いた建築生産に基づいていた)建設現場における職人仕事を機械化された制度へと入れ替える過程が貫徹することはなかった。明治維新後の近代化により日本で確立された新たな生産チェーンには封建的な構造が残存していた。この移行期間に設計された建築の形態には新たな生産手段との齟齬が含まれており、帝冠様式のように近代技術を用いてそれ以前の(主にはレンガや石やさらには木のような別の素材を基に構想されてきた)様式を再現するものであった。
戦後においては、丹下健三を筆頭とする近代建築家が、なおも影響力を保持していた前近代的な生産手段の残渣を克服するためのイデオロギー装置の構築を始め、それと同時に、新たな素材と技術に適合するものへと建築の設計を更新した。修辞的な戦略として、これらの建築家たちは「伝統」という概念を旋回軸として用いて、手工業的な生産を瓦解させ工業的手段を推進するような変化を起こそうとした。とりわけ丹下健三と池辺陽は近代建築が提供するより優れた手段と、近代的な産業や計画との連帯を利用して、生産過程をめぐる組織の前近代の名残と技術に対する消極的な態度を明確に攻撃した。職人的な手仕事は新たな生産様式に服従させられ、[型枠工のように] 近代的な労働組織に仕える場を与えられた。伝統論争はこのような広い範囲に及んだものであり、ひとつの側面だけから定義することはできない。しかし、1953年から1957年に掲載された論考の半分以上が技術や建設をめぐる問題を論じていることからも、この側面が伝統論争の共通問題として際立っていることが明らかである。
1953-1957年は川添登が「新建築」の編集者を務め、伝統論争が展開した時期であり、この期間に日本におけるセメント生産は1953年の8,768,000トンから1957年の15,176,000トンへと実質的に倍増した(Otaka 1963, 272-276)。無論、その要因を建築のみに帰することはできない。しかし、建築は社会一般に対するイメージとして、生産様式とデザインのギャップと、近代的な生活様式と伝統のギャップをともに橋渡しできる、訴求力のある形態を獲得することができた。
近代建築をめぐるイデオロギー闘争の只中で、ル・コルビジェは建築を通じてコミュニズムを招き入れた「トロイの木馬」だと糾弾されたことがあった(Fishman & Walden, 2021)。しかし、1940年代と1950年代の日本の近代建築の言説分析はこれと真逆の見解を与えてくれる。すなわち、近代建築は資本の蓄積と集中を必然的に促進するという見方である。根本的には一式の新たな工業技術とそれに必要な生産諸関係として、戦後日本の近代建築は、まだ残されていた熟練労働者たちの水平的な意思疎通と協働を解体することになり、技術的な図面や計画などの標準化されたプロセスによって労働力を統制するための、垂直的に階層化された権力の中枢を代わりに導入することになったのである。
Doctoral student in Tsukamoto Yoshiharu laboratory at Tokyo Institute of Technology.
参考文献:
1) Ashihara, Yoshinobu 芦原義信. 1954. “Impression of Japanese Exhibition House ビルの谷間に咲きいでた花[A Flower blooming among buildings].” Shinkenchiku 新建築, December: 32.
2) Ashikari, Zu 芦刈図. 1957. “We must prevent the idealization of “Jomon” debates “縄文”論議の観念化を防ごう―1956年の動きをかえりみて―.” Shinkenchiku 新建築, February: 73-75.
3) Bon, Ranko, and Yashiro, Tomonari. 2018. “Some New Evidence of Old Trends: Japanese Construction, 1960–1990.” In Economic Structure and Maturity, edited by Ranko Bon, 329–38. London: Routledge.
4) Cho, Hyunjung. 2012. “Hiroshima Peace Memorial Park and the Making of Japanese Postwar Architecture.” Journal of Architectural Education, vol. 66, no. 1: 72–83.
5) Clancey, Gregory. 2005. “Modernity and Carpenters: Daiku Technique and Meiji Technocracy.” In Building a Modern Japan, 183-206. New York: Palgrave Macmillan
6) Curtis, Paula. 2011. Purveyors of Power: Artisans and Political Relations in Japan’s Late Medieval Age. Columbus: Ohio State University.
7) Ferro, Sérgio. 2010. A história da arquitetura vista do canteiro. São Paulo: GFAU-USP.
8) Ferro, Sérgio. 2018. “Concrete as weapon.” Harvard Design Magazine, n.46.
9) Ferro, Sérgio. 2021. Construção do Desenho Clássico. Belo Horizonte: MOM Edições.
10) Figueiredo, Clara de Freitas. 2018. Fotografia: Entre Fato e Farsa (URSS — Itália, 1928–1934). São Paulo : University of São Paulo (USP).
11) Fishman, Robert, and Russell Walden. 2021. “From the Radiant City to Vichy: Le Corbusier’s Plans and Politics, 1928–1942.” In The Open Hand, edited by Russell Walden. Cambridge: MIT Press.
12) Fujimori, Terunobu 藤森照信. 1995. “Debate on Tradition 伝統論争.” Shinkenchiku 新建築, December (special issue “Trajectories of Contemporary Architecture: Architecture and Modernity in Japan Seen through Shinkenchiku 1925-1995 現代建築の軌跡:1925-1995「新建築」に見る建築と日本の近代”): 214–215.
13) Fujioka, Hiroyasu 藤岡洋保. 1991. “History of the Debate on Tradition 伝統論争の歴史.” Shinkenchiku 新建築 June (special issue “20th Century Architecture Part 2 建築20 世紀 PART2”): 78–79.
14) Fukai, Kazuhiro 深井和宏, and Mamoru Tohiguchi東樋口譲. 1996. “Function of Itazu: Design System of Vernacular Timber Houses by Japanese Master-Builders (1) 板図の機能: 木造建築の伝統的設計システムに関する研究 (1).” Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ), vol. 61, no. 488: 177–85.
15) Funo, Shuji 布野修司. 1981. Postwar Architectural Notes 戦後建築論ノート. Kanagawa: Sagami Shobo相模書房.
16) Hamaguchi, Ryuichi 浜口隆一. 1955. “The Most Representative Japonica and Positive and Negative Aspects of Collaborative Design 戦後最大の日本調と共同設計の功罪.” Shinkenchiku 新建築, July: 13-14.
17) Hamaguchi, Ryuichi 浜口隆一. 1956. “The Sukiya as a Problem of the Interior 内部の問題としての数寄屋.” Shinkenchiku 新建築, August: 57-59.
18) Hayama, Kazuo 葉山一夫. 1956a. “Recognition and Expression Should Not Be Confused in a Theory 認識論と表現論を混同すべきではない.” Shinkenchiku 新建築, July: 73.
19) Hayama, Kazuo 葉山一夫. 1956b. “Realist Method for Architectural Creation – The Goal of the Public Hall in Fukushima 建築創造におけるレアリズムの方法-福島教育会館がめざすもの.” Shinkenchiku 新建築, October: 30-33.
20) Ikebe, Kiyoshi 池辺陽. 1955a. “How to Deal with Japanese Design? 日本的デザインといかに取り組むか?.” Shinkenchiku 新建築., February: 41-43.
21) Ikebe, Kiyoshi 池辺陽. 1955b. “Learning from the Classics of Japanese Style 和風の古典に学ぶ(掲載題:和風建築と現在のデザイン).” Shinkenchiku 新建築, June: 66-69.
22) Inagaki, Eizo 稲垣栄三. 1959. Modern Japanese Architecture: The Process of Its Formation (1/2) 日本の近代建築―その成立過程 (上). Tokyo: Kajima Institute Publishing 鹿島出版会.
23) Ishida, Rie 石田理恵, and Ryuji 黒田龍二 Kuroda. 2004. “On the Drawing of Todaiji Daibutsuden 東大寺大仏殿内建地割板図について.” Summaries of Technical Papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan. F-2, History and Theory of Architecture, no. 2004, Architectural Institute of Japan: 113–14.
24) Isozaki, Arata. et al. 2011. Katsura Imperial Villa. Londo: Phaidon Press.
25) Isozaki, Arata.; Stewart, D. B.; Kohso, S. 2011 Japan-ness in Architecture. Cambridge: MIT Press.
26) Ito, Chuta 伊東忠太. 1984. “Discussing the True Meaning of Architecture and Deciding Its Character: I Hope That the Name Will Be Changed「アーキテクチュール」の本義を論して其譯字を撰定し我か造家學會の改名を望む.” Kenchiku Zasshi 建築雑誌, February: 195-197.
27) Iwata, Tomoo 岩田和夫. 1955. “Toward the Discovery of Tradition and the People 丹下健三の日本的性格―とくにラーメン構造の発展をとうして―.” Shinkenchiku 新建築, January: 62-69.
28) Iwata, Tomoo 岩田和夫. 1956. “Toward the Discovery of Tradition and the People 伝統と民衆の発見をめざして.” Shinkenchiku 新建築, July: 13-14.
29) Kuroishi, Izumi 2016. “Rethinking the Social Role of Architecture in the Ideas and Work of the Japanese Architectural Group NAU.” Review of Japanese Culture and Society, vol. 28, University of Hawai’i Press: 99–117.
30) Jacquet, B., et al. 2019. Le Charpentier et l’architecte: Une Histoire de La Construction En Bois Au Japon. Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
31) Meiji-mae Nihon Kagaku-shi Kankoukai [Publishing Association for Pre-Meiji Scientific History] 明治前日本科学史刊行会編纂. 1961. History of Japanese Architectural Technology before the Meiji Era 明治前日本建築技術史. Tokyo: Japan Society for the Promotion of Science 日本学術振興会.
32) Kōjiro, Yuichirō 神代雄一郎. 1956 “Meaning of Theories on Tradition by Architects 作家の伝統論の意義” Shinkenchiku 新建築, November: 68-69.
33) Kawazoe, Noboru 川添登. 1953. “Editorial Note 編集後記.” Shinkenchiku 新建築, July: 51.
34) Kawazoe, Noboru 川添登. 1958 Gendai Kenchiku Wo Tsukuru Mono [What Creates Contemporary Architecture] 現代建築を創るもの. Tokyo: Shokokusha彰国社.
35) Kon, Wajiro; Yoshida, Kenkichi 今和次郎, 吉田謙吉. 1931. Modernology 考現学採集:モデルノロヂオ. Tokyo: Kensetsusha 建設社.
36) Kuma, Kengo; Obuchi, Yusuke. “現代日本建築の四相 Four Facets of Contemporary Japanese Architecture: Theory.” UTokyo edX (online lecture) https://www.edx.org/course/four-facets-of-contemporary-japanese-architecture
37) Lin, Zhongjie. 2010. Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan. Oxfordshire: Taylor & Francis.
38) Maekawa, Kunio 前川國男. 1942. “Memorandum: On Tradition and Creation of Architecture 覚え書-建築の傳統と創造について” Kenchiku Zasshi 建築雑誌, December: 920-924.
39) Muramatsu, Teijiro 村松貞次郎. 1959. Nihon Kenchiku Gijutsushi [History of Architectural History in Japan] 日本建築技術史. Tokyo: Chijin Shokan地人書館.
40) Nakagawa, T. 中川武. 1986. On “Kiwari”, the traditional japanese architectural design method for the variation of the architectural structural scale 建築規模の変化と木割の方法. 日本建築学会計画系論文報告集, 362, 133–120.
41) Nakamori, Yasufumi. 2011. Imagining A City: Visions Of Avant-Garde Architects And Artists From 1953 To 1970 Japan. New York: Cornell University.
42) Nikkenkyo日建協 (Japan Construction Industry Workers Union Council). 2001. “Construction History 建設 歴史あれこれ.” http://nikkenkyo.jp/before/4joho/rekisiarekore/rekisiarekore.htm.
43) Nishiyama, Uzō 西山夘三. 1953. “Ethnic Tradition and National Issues in Housing Planning 住宅計画に於ける民族的伝統と国民的課題.” Shinkenchiku 新建築, November: 63-71.
44) Obata, S. 小畑精武. (n.d.). The roots of the downtown labor movement dating back to the Edo period Explore the history of the labor movement in downtown (1) 江戸時代に遡る下町労働運動のルーツ 下町の労働運動史を探訪する(1). 2018. http://gendainoriron.jp/vol.16/column/col05.php
45) Okamoto, Taro 岡本太郎. 1999. Nihon No Dentō [The Japanese Tradition]日本の伝統. Tokyo: Misuzu Shobo みすず書房.
46) Ōta, Hirotarō 太田博太郎. 1947. Nihon Kenchikushi Josetsu [Introduction to the History of Japanese Architecture] 日本建築史序説. Tokyo: Shokokusha 彰国社.
47) Otaka, Hideo. 1963. “The Cement Construction.” In Japan’s Construction: A General Review of Industries Related to Construction Activities, 272–76. Tokyo: The Overseas Construction Association.
48) Hoyano, Shigeo 梅干野成央, et al. 2019. “Architectural Works of the Master Carpenter Seiji Tateishi 大工棟梁・立石清重の作品.” Architectural Institute of Japan Technical Report 日本建築学会技術報告集, vol. 25, no. 60: 947–952.
49) Otaka, Masato 大高正人. 1956 “Public Hall in Fukushima: On the Design, Diversity of Functions – Grasping of the Complexity of Rural Life” 福島協会会館:福島教育会館の設計について 機能の多様性―地方生活の複雑さの把握.” Shinkenchiku 新建築, February: 20-21.
50) Adachi, Mitsuaki 足立光章. 1956. “Public Hall in Fukushima: Representation of People’s Tough Energy 福島協会会館:表現について 民衆の逞しい生活力を反映するもの.” Shinkenchiku 新建築, February: 21-22.
51) Kito, Azusa, and Toshihiko Kimura 鬼頭梓 & 木村俊彦. 1956. “Public Hall in Fukushima: Establishment of Skill – As Recovery of Skill in Huan Life 福島協会会館:技術の定着―それは技術の人間生活への復帰を意味する.” Shinkenchiku 新建築, February: 23-24.
52) Révai, József ヨージェフ・レーヴァイ. 1953. “Architectural Tradition and Modernism 建築の伝統と近代主義.” Bijutsu Hihyō 美術批評, October. 32-39.
53) Sakamoto, Tadanori 坂本忠規, and Kamata, Masahiko鎌田正彦. 2017. Report of the “Fushin Shitae-Zu Tatami-Ita ”: A Study of the Drawing Instruments in Pre-Modern Period in Japan 「普請下絵図畳板」について ~近世の製図道具に関する考察~. Takenaka Daiku Dougu Kan Kenkyu Kiyō竹中大工道具館研究紀要, vol.28: 21-39. https://doi.org/10.50862/dougukan.28.0_21
54) Shirai, Seiichi白井晟一. 1956. “The Jōmon: On Old Nirayama Residence of Egawa 縄文的なるもの 江川氏旧韮山館について.” Shinkenchiku 新建築, August: 4.
55) Shimizu, Norikazu. 2010. “The Establishment of the State-Owned Yawata Steel Works (1): The Integrated Steel Works That Promoted Japan’s Industrialisation When the Country Entered the Modern Industrial World as a Latecomer.” 九州国際大学経営経済論集, vol. 16, no. 01: 109-145. http://id.nii.ac.jp/1265/00000160/
56) Shimoda, Takashi. 2016. “History of Cement Manufacturing Technology.” Center of the History of Japanese Industrial Technology, Ed., Survey Reports on the Systemization of Technologies, vol. 23: 1–114.
57) Shiobara, Hiroki 塩原裕樹. “Dentō Ronsō (Controversies on Tradition) 伝統論争.” Arscape, Retrieved 25 March, 2022, https://artscape.jp/artword/index.php/伝統論争.
58) Stewart, D. B. 1987. The Making of a Modern Japanese Architecture: 1868 to the Present. Tokyo: Kodansha International.
59) Tange, Kenzō 丹下健三. 1948. “Problems on Construction 建設をめぐる諸問題.” Journal of Architecture and Building Science Architectural Institute of Japan 建築雑誌 , January: 2-10.
60) Tange, Kenzō 丹下健三. 1951. “Discussion on Architecture with Matisse 丹下健三:現代建築の課題「機械」と「手」との葛藤 マチスと建築を語る” Yomiuri Shimbun 読売新聞, September 3, 1951.
61) Tange, Kenzō 丹下健三. 1954. “Plan to Serve the Modernization of Tradition and People 伝統の近代化と民衆に奉仕するプラン.” Shinkenchiku 新建築, September: 25.
62) Tange, Kenzō 丹下健三. 1955a. “How to Understand Modern Architecture 近代建築をいかに理解するか.” Shinkenchiku 新建築, January: 15-18.
63) Tange, Kenzō 丹下健三 et al. 1955b. “Tange Laboratory: The Question Is Whether It Is Modern Architecture or Not – Views on Ikebe’s Paper 1 丹下研究室:近代建築かどうかが問題なのだ – 池辺論文に対する見解1.” Shinkenchiku 新建築, February: 44.
64) Tange, Kenzō 丹下健三. 1956a. “An Attempt to Establish a Creative Methodology Tange Laboratory創作方法論定着への試み 丹下研究室.” Shinkenchiku 新建築, June: 73-84.
65) Tange, Kenzō 丹下健三. 1956b. “The Creation of Modern Architecture and the Tradition of Japanese Architecture 現代建築の創造と日本建築の伝統.” Shinkenchiku 新建築, June: 29-37.
66) Tange, Kenzō 丹下健三. 1956c. “The Japanese Architect – Its Internal Reality and External Reality. 日本の建築家―その内部の現実と外部の現実.” Shinkenchiku 新建築, October: 7-13.
67) Tange, Kenzō 丹下健三, et al. “How Can We Overcome Tradition? 伝統をどう克服するか? シンポジウム:日本建築の進路.” Shinkenchiku 新建築, Mar. 1956d.
68) Tange, Kenzō; Asada, Takashi; Sachio Otani 丹下健三, 浅田孝, 大谷幸夫. 1954. “Hiroshima Plan 1946-1953. 廣島計画 1946-1953.” Shinkenchiku 新建築, January: 1-17.
69) Thompson, John B. 2013. Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. New Jersey: John Wiley & Sons.
70) Tokyo Metropolitan Library 東京都立図書館. 2020. “3. Site Allocation of the Edo Castle Honmaru Main Tower 3.江戸城御本丸御天守百分之一建地割.” https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/collection/features/digital_showcase/001/03/.
71) Uchida, Yoshichika 内田祥哉, et al. 1955. “UHON Group: There Is No Need to Be Conscious of Japanese Design – Views on Ikebe’s Paper 3 UHON Group日本的デザインを意識する必要はない – 池辺論文に対する見解3.” Shinkenchiku 新建築, February 45-46.
72) Wachsmann, Konrad コンラッド・ワックスマン. 1956. “Enthusiastic Words by Wachsmann ワックスマン大いに語る.” Shinkenchiku 新建築, February: 53-56.
73) Watanabe, Yasutada 渡辺保忠. 1955. “Technology and Styles in Ancient Architecture 古代の建築生産における技術と様式.” Shinkenchiku 新建築, March: 11-12.
74) Watanabe, Makoto Shin, et al. 2013. “KENCHIKU / Architecture from Japan.” Wochi Kochi Web Magazine. https://www.wochikochi.jp/english/special/2013/09/japan-of-modern-architecture.php
75) Yamagishi, Yoshihiro 山岸吉弘. 2017. “建築生産史(近世).” Kenchiku Shigaku 建築史学, vol. 68: 70–84.
76) Yamamoto, Gakuji 山本学治. 1956. “The Development of Modern Architecture and the Consciousness of Tradition 現代建築の発展と伝統の意識.” Shinkenchiku 新建築, July: 2-5.
註
註1) 一般に、伝統論争の期間は藤森照信(1995, 214-215)の研究による1955-1957や、オンラインで広く読まれる記事(塩原, 2022)の1955-1956などの諸説があるが、本稿では著者たちの一次資料の調査に基づき1953年を発端とする。
註2)歴史区分上の「前近代」には諸説あるが、本稿では明治維新以前を前近代とする。
註3)著者はこれらの全記事リストをまとめた論文を準備中である。
註4)伊東の提唱以前から「建築」という言葉が当時まだ「造家」の名を冠していた学会の機関紙「建築雑誌」と学会規則に正式に用いられていたことは明記されるべきだろう。伊東はふたつの訳語の混乱を示すため「第五條: (…) 正員は建築学を”, “第十條: (…) 建築専門の學校に在て”, “第廿八條: (…) 建築雑誌と名け」の箇所を参照している。Watanabe, M. S. et al. (2013) も参照せよ。また、 Jacquet et al (2019, 10)によれば、伊東忠太の最初の1898年の博士論文(法隆寺建築論)は寺社のディティール分析を通じてすでに伝統について論じている。
註5)太田博太郎は「職人」と「工匠」という用語を、たとえば頁179の最初のふたつのパラグラフのように、同義語として併用している(太田1947)。本稿では「職人」に統一する。
註6)当時の日本における建設行為は階層的な経済機構における複雑なエージェントのネットワークを形成し、職人は生産のみならず取引や政治にも関わった。貴族階級は官吏や指南役を用いて職人との関係を築き、数世紀をかけて、職人の仕事を権力関係へと同化する内部機構を発展させた。資金と生産の複雑な関係性は、様々な称号と職務を通じて、職工と皇室や大名との連帯を生み出した。Curtis (2011)は近世後期に本格的な国内交易の市場が生まれるやいなや、職人の技巧は地方間の権力闘争の中心的な位置を占めるようになったことを示している。
註7)日建協 (2001) 等
http://nikkenkyo.jp/before/4joho/rekisiarekore/rek.
註8)稲垣栄三によれば、正式な職人組合は幕府の管理下にあったものの、一定の自律性を有していた(稲垣1959, 49-53)。さらに、特に江戸中期以降は、都市における建築需要の高まりと(村落から都市へ逃れてきた人口からなる)非熟練大工の増加を下地として、(幕府が正式に任命した「棟梁」とは異なるものとしての)「町棟梁」に率いられた民間の職人連盟が生まれ、これらは公設の組合が完全には管理できないものとなった。
註9)坂本忠規と鎌田正彦はこの用途の古い図面の存在が17世紀に遡れることを示した(坂本・鎌田 2017)。しかし、ツールとしてのこうした図面より普及するのは19世紀であり、それらは高価で希少な舶来品を真鍮に写したものだった。
註10)石田理恵と黒田龍二は奈良の東大寺大仏殿の工事に用いられた1688年の板図を分析している(石田・黒田 2004)。しかし、この時代(17世紀)からのそうした考古学的な発見は極めて稀なものであり、職人たちはこの技術を用いていたものの、一般的な実践ではなかったことが示唆される。図面や板図は18-19世紀により普及したと考えられる。
註11)日本を1945年の焼け跡から1960年代の世界二位の経済大国にまで導いた産業化の圧力の基礎とは民間の建設産業の発展があり、1960年にはGDPの17.6%を占める産業となっていた(Bon & Yashiro, 2018, 329–38)。
註12)題名はジェフリー・スコットの著名な『ヒューマニズムの建築(The Architecture of Humanism: A study in the history of taste) 』(1914)と偶然一致しているが、浜口にとっての「ヒューマニズム」は機能主義を意味しており、むしろH.P.ベルラーヘの『建築の発展と基礎(The foundations and development of architecture)』(1908)にみられる折衷主義への抗戦と労働者開放のための倫理的な道筋としての無装飾の近代建築の賞賛という系譜においてよりよく理解されるものである。
註14)西山は、「機能」という言葉はそこに含まれる共約不可能な複雑性にもかかわらず不明瞭かつ恣意的に用いられていると考え、「建築の機能は多様で互に對立している」「我々がここで機能主義の積極的な面を活かそうとするならば、まずその問題點が『[無批判的に受容された度々資本主義的な機能群としての] 機能にしたがつて建築する』という點ではなして『いかなる機能をとりあげるか』という點にある」と主張した (西山 1953, 65)。
註15)西山のこの観点は、その一月前(1953年10月)にハンガリーの文化大臣であるジョセフ・リーヴァイ(1953)によって書かれた記事と方向をともにしている。
註16)生まれつつある新たな伝統としての近代建築という前川の概念とジークフリード・ギーディオンの1941年の著作『時間・空間・建築(Space, Time and Architecture: The growth of a new tradition )』にみられる近代建築観は類似しているが、前川によるギーディオンへの言及はなく影響関係は本研究時点では特定できなかった。同様に、ギーディオンの名は伝統論争の文脈においても触れられることはなかった。『時間・空間・建築』の第一版は太田實の翻訳により1955年5月に国内出版されており、川添(1958, 124)はギーディオンの時空間概念がこの出版以前にすでに建築家の間で受容されていたことを認めているが、近代建築を新たな「伝統」の成長とするギーディオンの議論が日本の伝統論争で明示的に援用された例は見当たらない。
註17)Japonica 「ジャポニカ」は、池辺による「日本的デザイン」への攻撃(池辺 1955a)と似たかたちで、近代建築への日本的要素の折衷主義的な適用を批判する言葉である。この言葉は伝統論争において岩田知夫(岩田 1955)等によるいくつかの記事でも論じられた。
註18)岡本太郎自身が縄文概念の推進者として伝統論争に直接的に関与していなかったことは言及に値する。この時期における岡本の「新建築」誌への登場は日本庭園についての論考のみであり、そこでは縄文についての言及は一切なかった。縄文を論じる岡本の書籍は1956年に出版され、建築評論家の神代雄一郎は同年11月号の「新建築」に掲載された書評でその信頼性を批判的に検討している。
註19)これらの論考をより組織的にまとめた論文を著者は準備中である。
註21)オスカー・ニーマイヤー(1940年のパンプーリャのプロジェクト)や晩年のル・コルビジェ(ロンシャン等)等の建築家たちもこうした技術や生産体制の影響について言及している。
註22)このペンネームの「図」の発音は特定できなかった。本稿ではこの字の最も典型的な読みの「ず」を仮に採用している。
KAGAWA PREFECTURAL GOVERNMENT OFFICE (1954-1958)
Photographs specially taken in 2022 for this article, by Gabriel Kogan